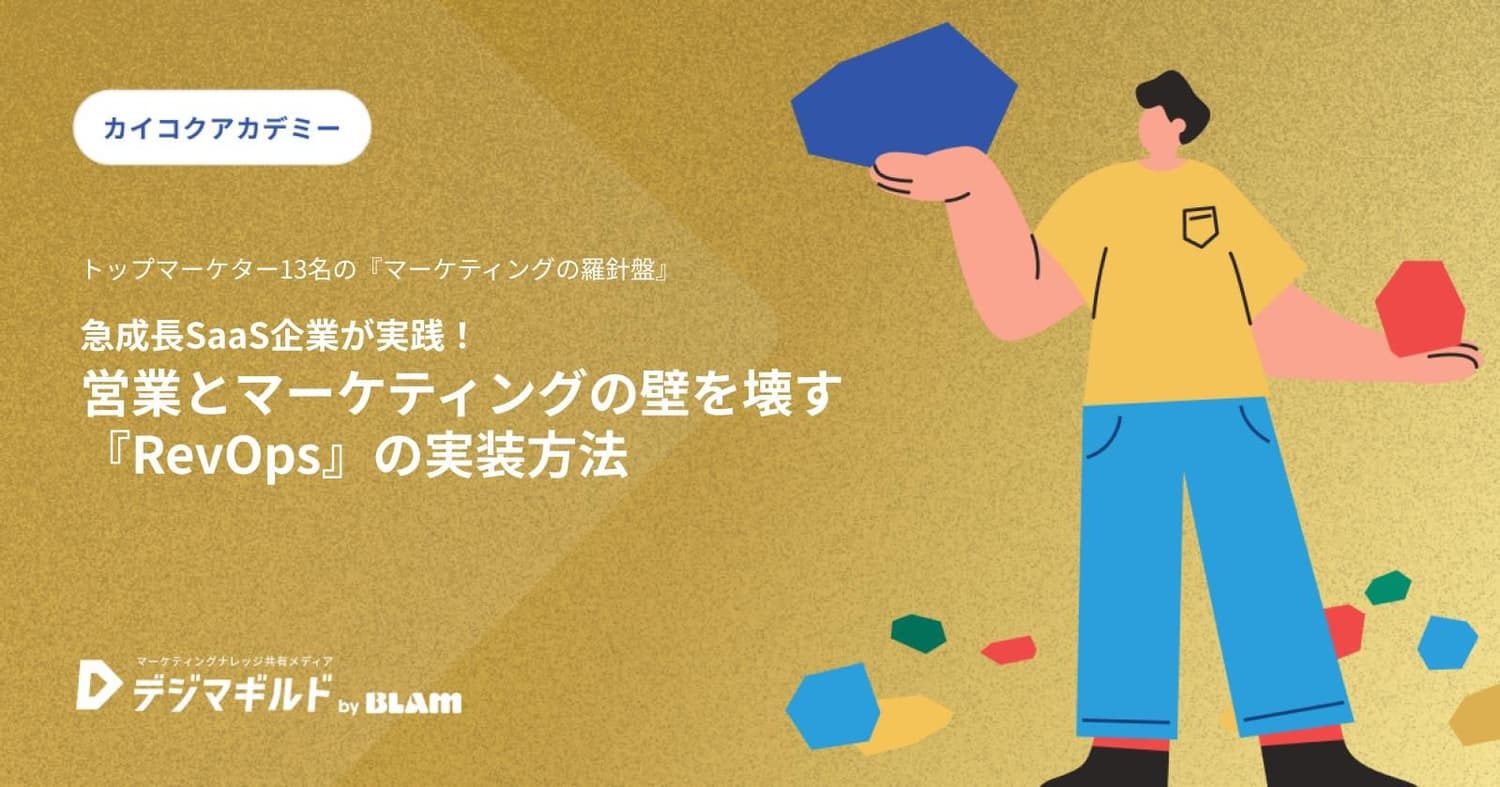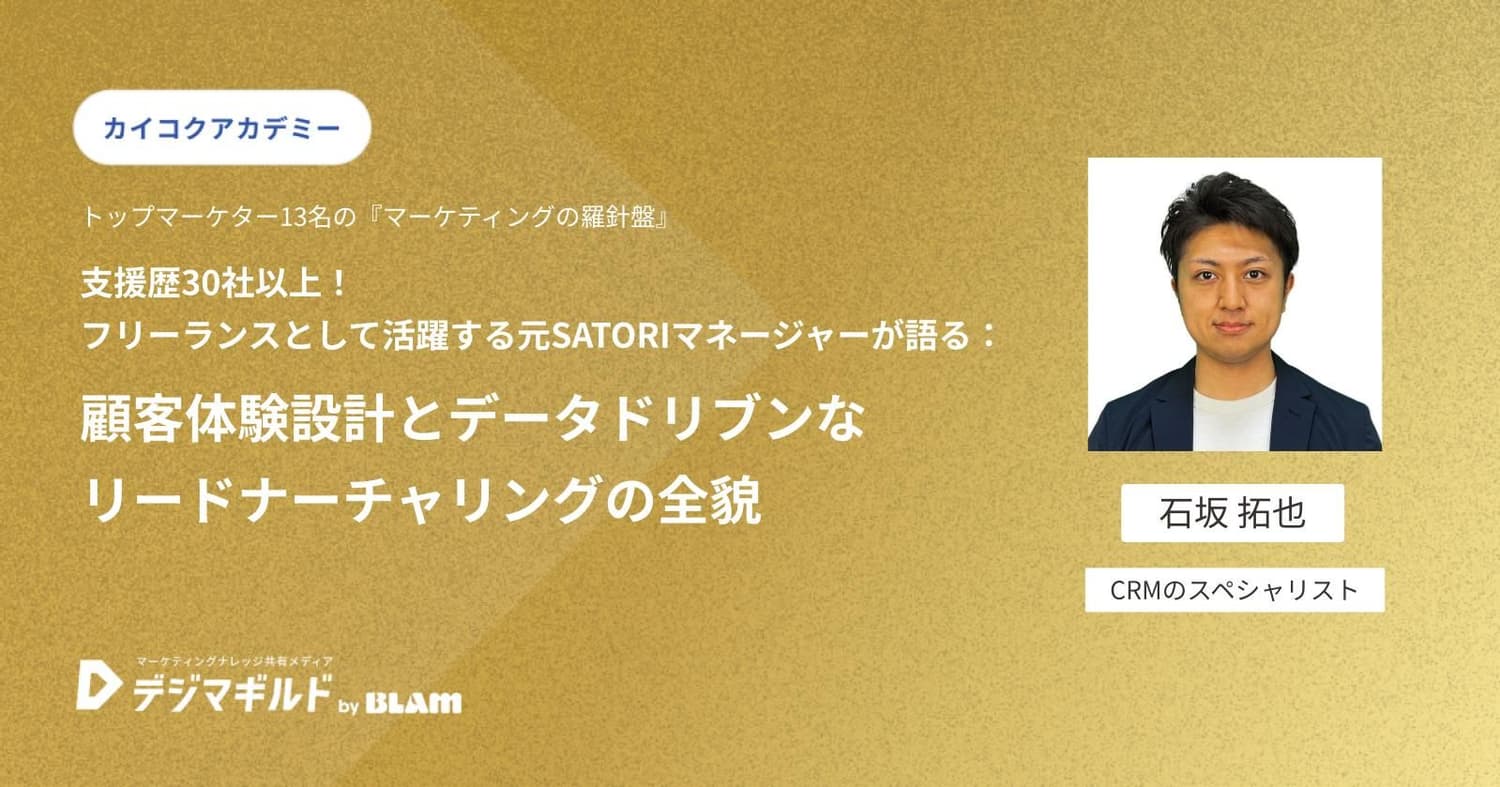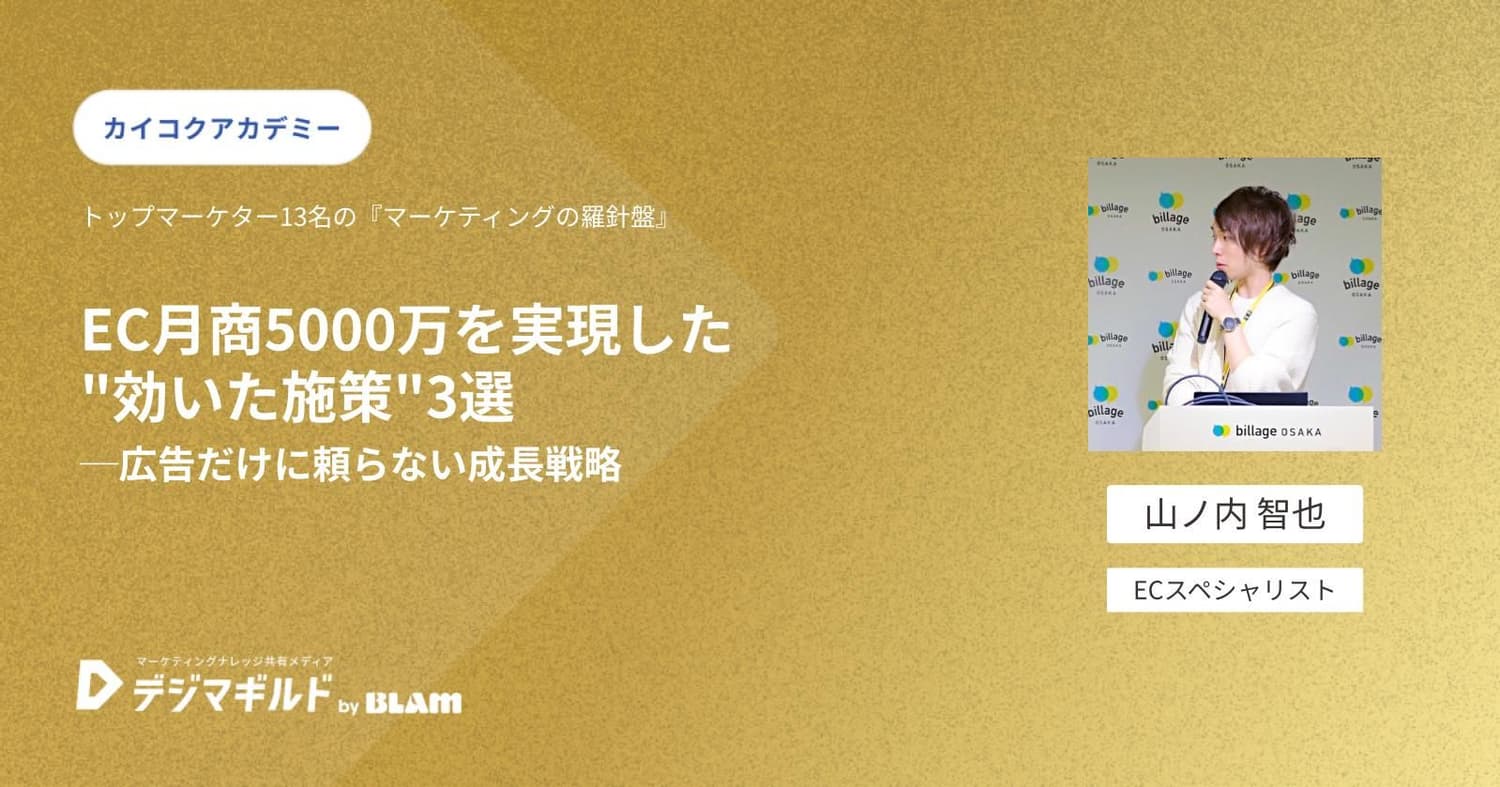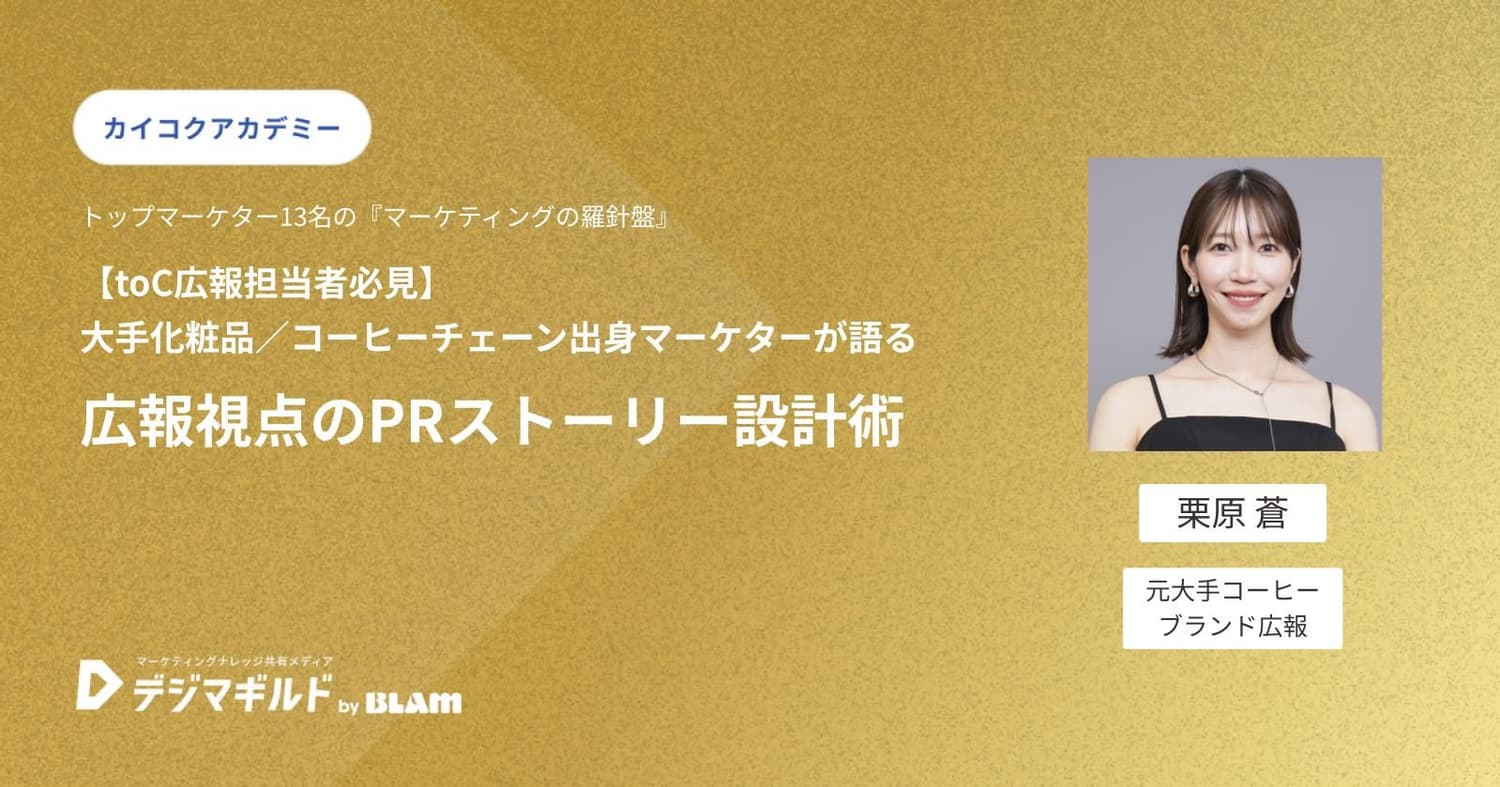
広報で伝えるのは"商品情報"ではなく"問い"
広報の仕事をしていると、こんな感覚に陥ることはないでしょうか。
「頑張ってプレスリリースを書いたのに、なんだか生活者の反応が薄い」 「商品に差別化要素が薄く、結局メディアに伝えられるのはスペックと事実だけ」 「共感が大事とは聞くけれど、それってどうやってつくるの?」
SNSの保存数もメディア露出も悪くはない。でも生活者の頭にも心に残っている感じがしない。特にBtoC領域の広報では、「伝えているのに、本質的には伝わっていない」というもどかしさが付き纏います。
私自身も、広報の仕事をしている際に何度も同じ壁にぶつかりました。どんなに高機能で、こだわりや想いが詰まった商品でも、「うちの技術、すごいでしょ?」と語るだけでは、生活者やメディアからの共感が生まれなかったのです。
そしてあるとき気付いたのは、商品の強みをそのまま語るのではなく、生活者の問いや悩みに答えるストーリーに変換することが必要だということ。
もちろん、知名度や人気度によっては、新商品情報を出せばすぐに話題や共感を生むブランドもありますが、それは限られたブランドの特権と言えるでしょう。
本記事では、私自身の失敗と試行錯誤を通じて見えてきた、"共感を起点とした広報設計"の考え方と実践プロセスを、具体的なエピソードを交えながらお伝えします。尚、BtoC商品を中心に解説しますが、基本的な考え方はBtoB企業でも応用可能です。
が
課題解決をサポート!
共感を生まない理由は「ストーリーの主語が企業になっているから」
共感を生まない広報とは、言い換えれば「スペックや機能の押し売り」です。
- 新機能
- 特許技術
- 高品質な原料
など、社内では熱量高く語られ、開発者も誇りを持っている。
しかしながら、モノや情報が溢れかえっている現代では、それらが生活者の悩みや関心とうまく接続していなければ、本当の意味では届かないと考えます。
なぜなら生活者は、単なる商品やサービスそのものではなく、「自分の課題や悩みを解決してくれるかどうか」「未来の自分をよくしてくれそうか」を無意識的に判断し、モノや情報に取捨選択しているからです。
加えて現代では、生活者自身もまだ気付いていない違和感や満たされなさ──いわゆるインサイトに着目し、それに応えることができるかどうかも、共感や支持を得るうえでますます重要になってきています。
そのため、「これは私のための商品だ」と思ってもらうには、単なる機能の羅列ではなく、そう感じてもらえる文脈や共感されるストーリーをどう設計するかが問われているのです。
失敗から学んだ教訓
実際、過去に担当した商品で、開発チームが誇りに思っている技術的優位性をそのままメッセージにしたところ、専門的なメディアでは評価された一方で、一般向けメディアや消費者からの反応は低調だったことがあります。「企業が伝えたいこと」と「消費者が知りたいこと」のギャップを埋められていなかったのが原因でした。
この失敗を経て、商品の機能ではなく、その機能がなぜ必要なのかという価値の必然性を示すことの重要性を痛感したのです。
実体験:商品機能ではなく商品価値の必然性を示した広報メッセージの構築
とあるウェルネス系商品のローンチに携わったときのこと。その製品は、競合他社よりも「より広い範囲の部位に使えて利便性が高い」という機能性が特徴でした。
この機能をどう伝えるか社内で検討を重ねた結果、当初は「○○にまで使える!」というスペック重視の打ち出しになりかけていましたが、改めて消費者視点に立ち返った時に、
「広範囲に使えることが、生活者にとって本当に響くポイントなんだろうか?」 「スペックの凄さではなく、そのスペックがなぜ必要なのかを語らなければ、伝わらないのでは?」
と考え、アプローチを一新。
どこをケアすべきかという主観的な意識ではなく、"他人にどう見られているか"という視点に着目し、消費者への意識調査を実施しました。
結果、多くの人が、自分が気にしているパーツと、他人から見て目につくと感じられているパーツは、必ずしも一致していないという意外な発見が。つまり、本人はノーマークだった部分にこそ、他人の視線が集まっていたのです。
この気づきをもとに、「セルフイメージでは見落としがちな"印象のズレ"に気づき、そのギャップを埋めるケアこそが必要」というストーリーにシフトして、メッセージを再構築。「印象のズレがあるからこそ、○○だけでなく広い範囲へのアプローチが求められる」と価値を翻訳し、調査リリースからCMに至るまで全てのメディアにおいてコミュニケーションを統一しました。
商品のスペック説明にとどまらず、「自分自身の印象を見直すきっかけになるアイテム」として位置づけたことで、生活者からの共感を得つつ、商品自体を自分ごととして捉えてもらうことができました。
さらに、これまで語られることの少なかった、"セルフイメージと他者評価のズレ"という切り口を数値データで可視化したことでニュースバリューが生まれ、結果的にキー局TV番組や雑誌、主要Webメディアなどで紹介される成果につながりました。
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
「伝えたいこと」を「伝わる言葉」に変える。共感される広報ストーリーの組み立て方
上記のように、企業が伝えたい機能や性能のことよりも、生活者が日頃感じている悩みや違和感、まだ自分の中でも言語化できていない気付きを捉えてはじめて「私のための商品」として届き、メディアにも報道価値のある商品として受け入れてもらうことができます。
では、具体的にどうすれば生活者やメディアに共感される広報メッセージを作ることができるでしょうか。
ここからは、広報・マーケティング担当者が日々の業務で実践できる、「共感設計」の具体的なステップをご紹介します。
目指すのは、単なる製品説明を超えて、生活者の感情に届くストーリーを組み立てることです。そのために必要な視点と思考プロセスを、実務ベースでまとめました。
STEP1|「自社商品の素材を棚卸しする」
こだわり・強み・背景を徹底的に言語化するというステップです。
製品にまつわる技術・商品特長・使い方・使用感・製造工程・開発者の想いなど、「企業が語りたいこと」をすべて書き出します。機能と想いの両面から棚卸しすることで、広報ストーリーの素材を整えていきます。このステップで開発の背景にある解決したい問題や、ターゲットとなるユーザーの想定像なども一緒に並べておくと、次のステップで変換しやすくなります。
STEP2|「そのこだわりは、生活者にとってなぜ必要かを問い直す」
視点を消費者目線に切り替えて、自分ごと化できる理由を探るステップです。
STEP1で挙げた各要素について、「これは誰の、どんな悩みに対して機能するのか?」を徹底的に掘り下げます。ここでポイントとなるのは、「○○だから便利」ではなく、「○○に困っていた人にとって、なぜ助かるのか?」まで踏み込んで考えることです。
STEP3|「商品の機能を共感できる言葉に翻訳する」
商品の魅力を、生活者の感情や実感に届く言葉へと言い換えるステップです。
スペックやこだわりをそのまま語るだけでは共感は生まれません。大切なのは、「それって、まさに私のことだ」と感じてもらえるような、生活者視点の言葉に変換することです。
例)
- 企業視点:エイジングケア成分を配合(企業の伝えたいことに終始)
- 生活者視点:"30代に入ってから「今日疲れてる?」と聞かれることが増えたあなたへ"
このステップに取り組む際に私がヒントにしているのは、商品レビューやSNS投稿で出てくる本音です。消費者が感じた、恥ずかしさや小さな不安の中に共感される言葉の種があるので、該当商品やサービスのPR表現を3パターン以上書き換えてみることをおすすめします。
STEP4|「理想的な露出内容を想定し、逆算で企画設計する」
最後は、どのメディアで・どんな文脈で取り上げられたいか?その読者はどんなことを考えているのか?という掲載像をあらかじめ描くステップです。
掲載メディアや枠に合うストーリーを逆算して企画内容を考えることで、「誰に」「どんな切り口で」「何を伝えるか」がさらに明確になります。ここでのポイントは、媒体特性や編集方針を把握したうえで、「この商品ならどう扱われるか?」を自問自答し、企画を練ることです。実践例は以下の通りです。
- どのメディアに取り上げられたい? → 美容誌A、女性誌B
- そのメディアのどんな特集で取り上げられたい? → 働く30代の手抜きに見えないヘアケア特集
- その特集で紹介されるであろうアイテムの共通点は? → 手間はかけられないけど、丁寧にケアしたように見せられる特長を持っていること
- 商品スペックをどう言い換えれば届く? → 「朝の簡単1ステップで、ちゃんとヘアアイロンをした感が出せる」「毎朝に5分の余裕をつくるアイテム」
このように、「伝えたいこと」から考え始めるのではなく、「誰の、どんなモヤモヤや課題に応えるのか?」から逆算して言葉を選ぶことで、共感性は大きく高まります。
おわりに:広報とは、「翻訳」の仕事である
広報という仕事は、情報をそのまま発信するのではなく、生活者に伝わる言葉や見せ方へと翻訳すること。
本質的な商品の魅力を届けるには、こだわりや技術を語る前に、受け手の感情や悩みに目を向け、「どうしたら心に届くか?」「自分ごと化してもらえるのか」を考えるストーリー設計が必要だと考えます。
「いいものを作ったのに、なぜ響かないのか」
その答えは、「伝えていること」ではなく、「伝え方」にあるかもしれません。
技術やスペックの伝達者ではなく、共感と納得を生むストーリーテラーとしての広報の第一歩は、生活者の言葉に耳を傾けることから始まるのではないでしょうか。
が
プロをマッチング!
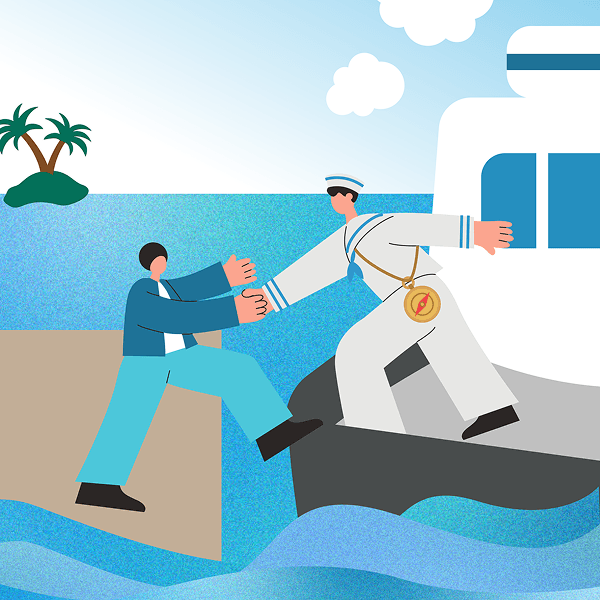
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人
栗原 蒼
元大手コーヒー ブランド広報
大学卒業後、日系化粧品メーカーや外資系コーヒーチェーンにてPR業務に従事し、広報戦略からプロモーション施策に至るまでコミュニケーション領域を担当。独立後はファッションやライフスタイル、ビューティ業界を中心にPR支援をする傍ら、広報講師・キャリアコーチとして組織や個人の育成・伴走支援にも取り組んでいる。