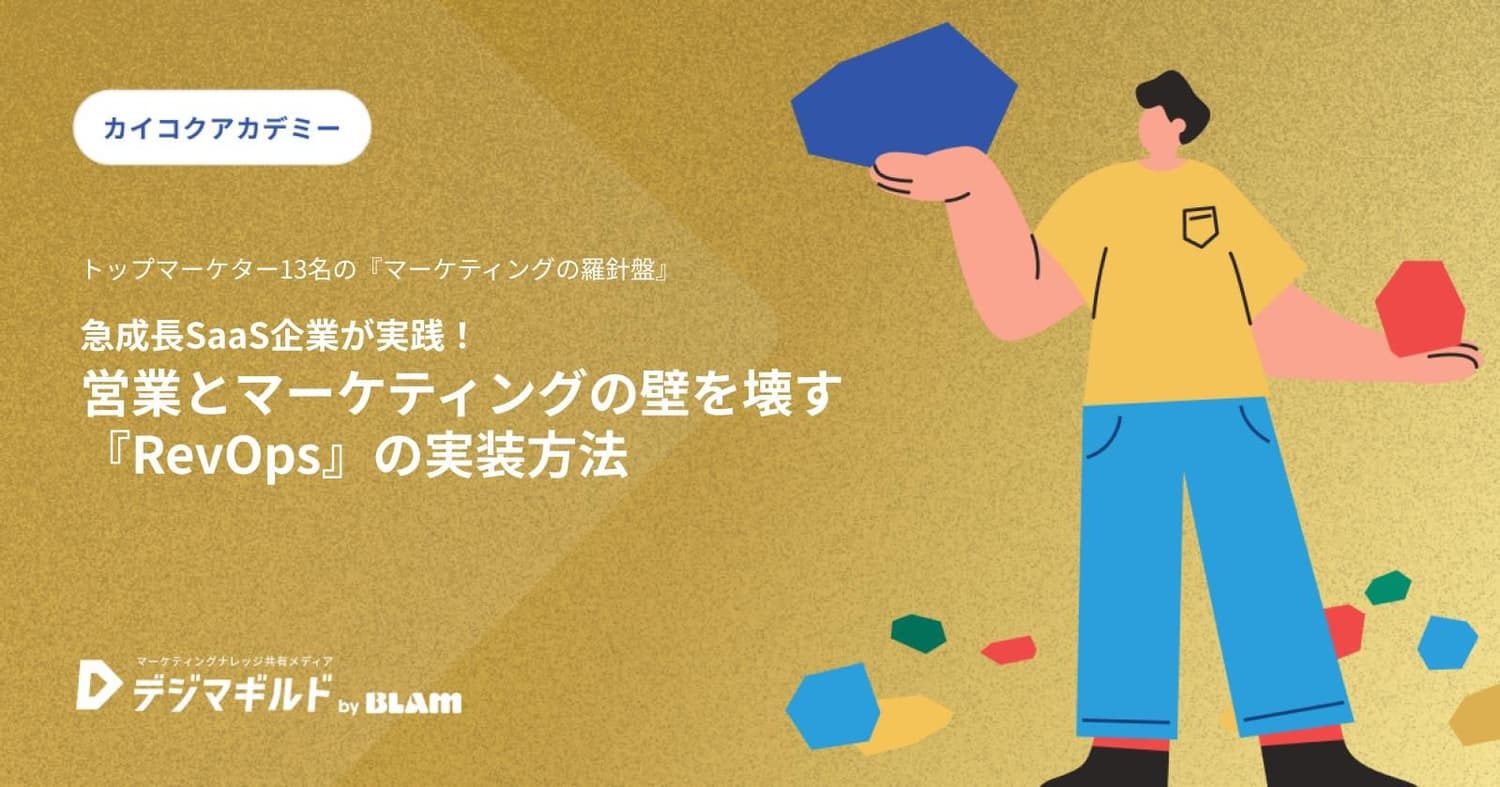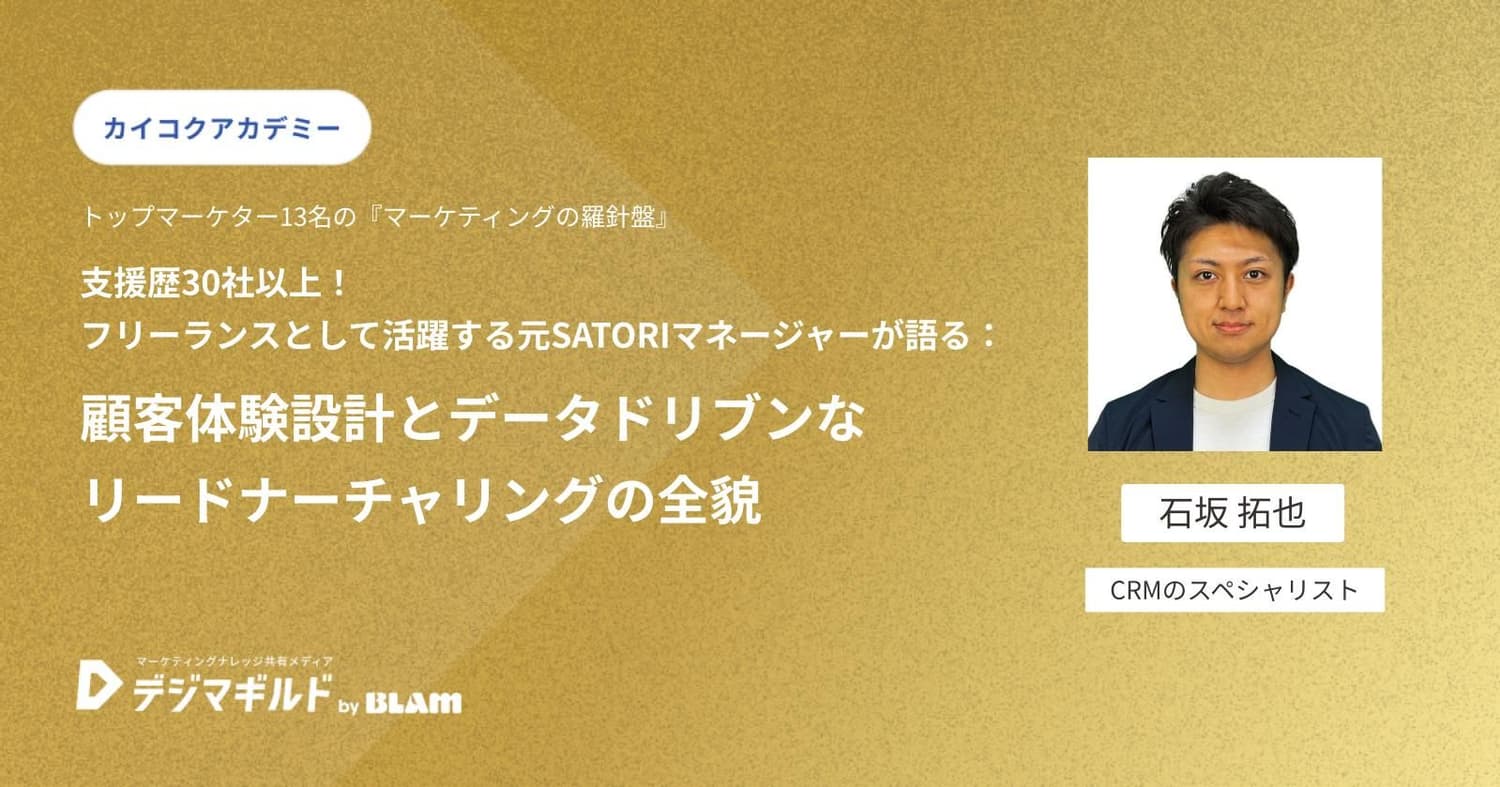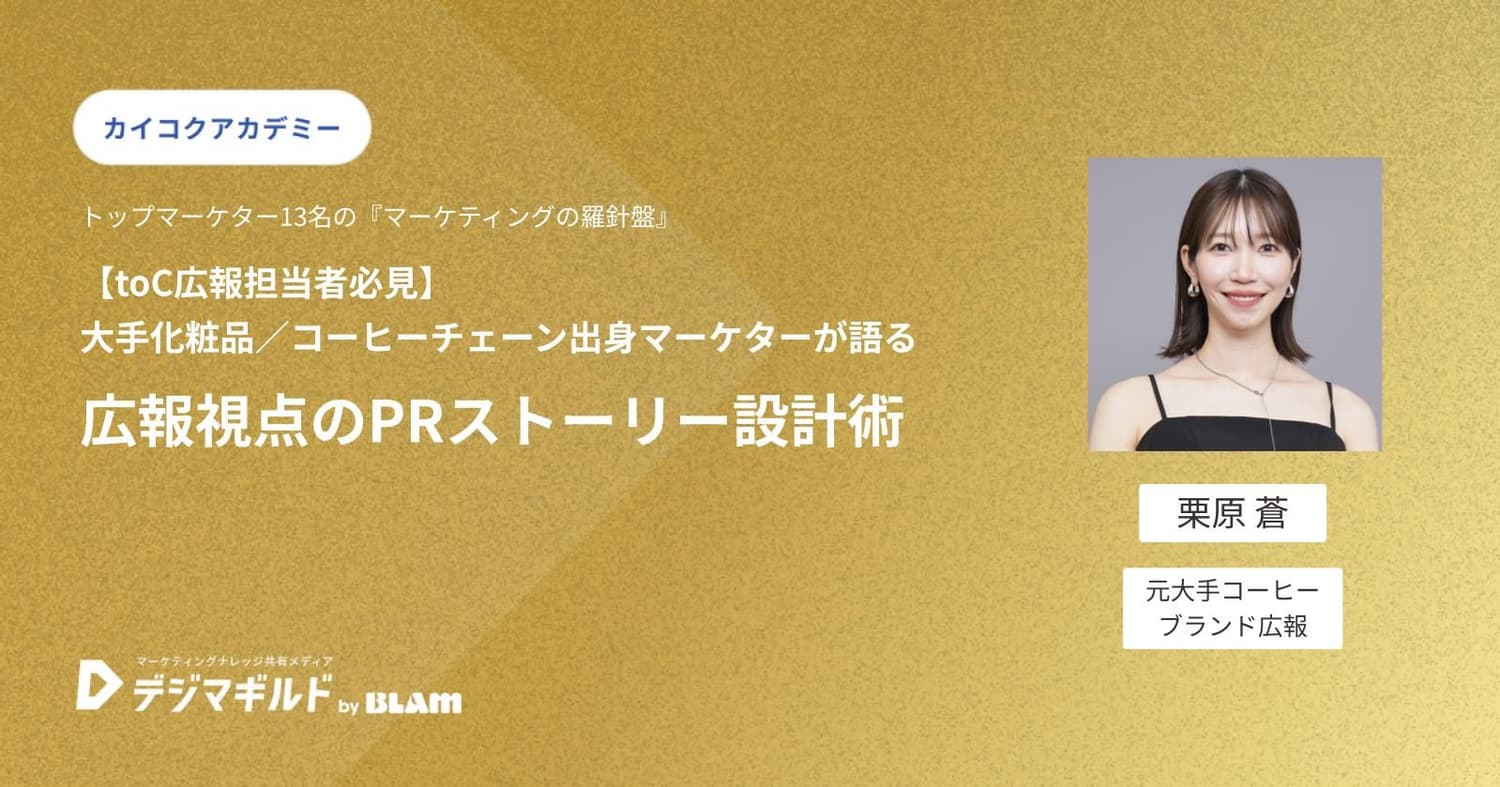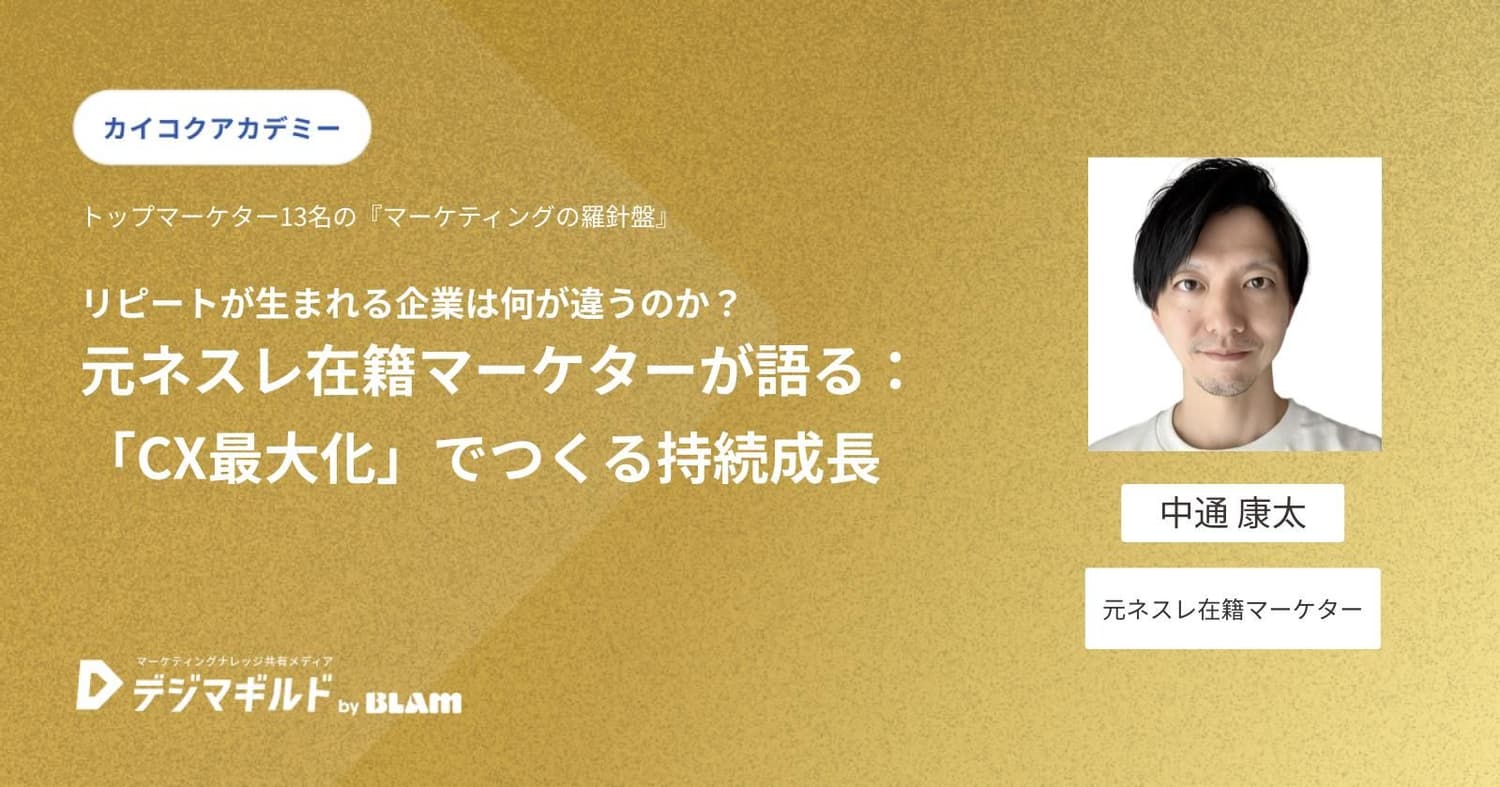
はじめに:ビジネス成長のカギは「リピート」にある
真にビジネスを持続的に成長させる要素は何かと問われたとき、共通して語られるのが「リピート」の重要性です。
理由は明快です。新規顧客の獲得コスト(CPA)は年々上昇しており、一度獲得した顧客をいかに維持し、継続購入へ導けるかが、利益の安定性と成長性を左右します。リピートが仕組みとして回り出すと、安定成長が可能になります。
このリピートを生むために、最も重要なのが「顧客体験(CX)の最大化」です。しかし重要なのは、「CX=プロモーション、コミュニケーション施策」だけではないということです。マーケティング視点におけるCXとは、4P全体──Product(商品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(伝え方)──で総合的に作られるものです。
が
課題解決をサポート!
マーケティングにおけるCXは4P全体で設計される──誤解しやすい落とし穴
マーケティング現場で起きがちな誤解が「SNSを強化すればCXが改善する」「CRM配信を増やせばリピートが生まれる」といった、コミュニケーション施策偏重の発想です。しかし現実はもっとシンプルです。
たとえば、いくらリッチな広告を出しても、そもそも商品が期待外れなら顧客は二度と戻りません。口に合わなかったラーメンをまた食べたいとは思いません。また、価格が割高に感じられれば、どれだけ素敵な世界観を伝えても一度きりの購入で終わります。つまり価格に対して得られた価値が上回らなければ次の購入は生まれません。また、購入体験やサポート体験が悪ければ、いくら広告やSNSでコミュニケーションの発信頻度を増やしても顧客は帰ってきません。
顧客体験は、マーケティングにおいては4P領域で総合的に作られます。
- Product(商品):リピートされる前提は、そもそも「また買いたい」と思わせる商品力
- Price(価格):購買頻度に応じた価格設計、納得感のある価格が不可欠
- Place(流通・購買体験):買いやすい場所、使いやすいUI、速い配送
- Promotion(伝え方):Topofmindの獲得、購入理由・価値作り
顧客は企業のすべての接点で体験を感じ取っています。リピートは広告やCRMのコミュニケーションだけで成立するものではなく、ビジネス設計全体で生まれるものです。
CXの起点は「顧客理解」にある
CX設計の第一歩は「顧客理解」です。なぜなら、リピートは「企業が届けたい情報」ではなく、「顧客が欲しい、もしくは必要な体験」を正確に捉えたときに最大化されるからです。マーケティングでよくある失敗は「こう思われているはず」「この訴求が響くはず」といった思い込みです。しかし成果が出る企業は、事実ベースで自社の顧客を理解し直します。
基本の問いはとてもシンプルです。
- 自社顧客は誰か?誰がどのくらいいるのか? 顧客層の構成と行動特性
- 彼らはなぜ買うのか? 何を満たすために選ぶのか?
- 何が購入の障壁になっているのか?
とてもシンプルなのですが、シンプルが故にこの問いに答えらえる担当者は実はあまり多くありません。こういう情報をベースにマーケティング戦略、コミュニケーション戦略を設計していくと成功確率が上がります。
そしてそこから個別の戦略や戦術におとしていくのですが、例えばメルマガやSNSなどのコミュニケーションを設計する際にも、
- 誰に向けて発信しているのか?どういう状態でその情報を受け取るのか?
- 何を知ってもらえれば買うのか?顧客の何の課題が解決できるのか?
- 何が購入の障壁になっているのか?
といったことをベースに組み立てるのが良いです。また、ここまで考えているときちんと仮説が立てられているのでPDCAがしっかり回せるため、企業のマーケティングレベルの向上が図れるという利点もあります。
顧客を理解することで、ターゲットも施策も変わります。「誰の、どんな課題を、どう解決するか」を明確にしない限り、効果的なCX改善もリピート施策も成立しません。
が
プロをマッチング!
SNSの目的を変えたら成果が10倍になった話
この顧客体験を重視することで数字が上がった例を紹介します。外資メーカー勤務でデジタルマーケティング全般を担当していた時代の話です。
私がその組織にジョインした時にはWEBサイトの集客数がKPIであったために、SNSからもWEBサイトへの導線がひかれており、ここへの送客数がKPIとなっていました。しかもなるべくWEBサイトに飛ばしたいがゆえに、SNSで投稿している情報は限定的で、それだけ見てもよくわからない情報でした。
しかし本質的には、ビジネス指標の売上に対し、どのようにコミュニケーションでそこに寄与するのかというと、”顧客に対して届けたい情報を正しく届ける”ことであって、WEBサイトに人を連れてくることではありません。
また、顧客体験から考えると、SNSからWEBサイトへ遷移させる挙動というのは、一種の娯楽時間や隙間時間の中でフィードを見ている状態から、別の作動と表示までの待ち時間を顧客に強いることになり、それはユーザーにとって好ましい状態ではないし、事業会社としても別に望んでいる体験ではありません。
なので、”伝えたい情報”を正しく精査し、その情報をコンパクトにSNSで掲載する、さらに詳細が知りたい人にはサイトで情報を得てもらう、という導線に変更しました。これによって同じようなメッセージの投稿でもエンゲージメント数が10倍前後に推移するようになりました。このように、顧客体験をベースに施策の設計を行うことで、本来伝えたいことも伝えることができ、担当者の目標数字にも寄与し、そして顧客にとっても欲しい情報がタイパよく心地よく入手することが出来る、という状況を作ることが出来ます。
成果を生む「事実→戦略→戦術」の思考法
上記は分かりやすい単なる施策の一例ですが、組織全体、企業としてCXを軸に成果を出すためには、いくつかのステップを踏むことが必要です。ここでは理想的な設計の仕方をご紹介します。
外注か採用か迷ったら
へ相談!
パーパスから全ては始まる
企業は「パーパス(存在意義)」に基づき、企業戦略、事業戦略、マーケティング戦略が構築されます。そしてそのパーパスに共感を得たとき、顧客のロイヤリティやエンゲージメントは格段に向上します。なぜなら「その企業が存在する理由」に顧客が共鳴し、「応援したい」と思えるからです。
ステップ1:事実の特定
まずは「事実」を正確に把握します。
- 今の顧客層は誰か?
- 上位売上層は誰で、離脱はどこで起きているのか?
- 自社の何に価値を感じ、何に不満を抱いているのか?
事実を見ずに戦略を作ると、戦術がズレやすくなります。
ステップ2:戦略の策定
次に明確なターゲット設定と提供価値を定義します。
- どのようなビジネス課題の解決を目的にするのか?KPIは?
- KPIを達成するのに十分な、誰の何の課題を解決するのか?
- その課題を解決できる自社が提供すべき「価値」は何か?
- それを提供するために必要なリソース配分はどのようなものか?
ここでパーパスとの整合が取れた戦略であることが大事です。
ステップ3:戦術の実行
最後に戦術が決まります。
- 何の商品を、いくらで、どこで、どう届けるのか
- どのメディアを使い、どの接点でコミュニケーションするか etc.
この順番を守ることは大事です。最初から「TikTokが流行っているからやる」では戦術先行の迷子状態になります。戦略なき戦術の実行は、単純に失敗確率が高くなるだけでなく、会社全体としての顧客に対するコミュニケーション齟齬の発生(ex.高級ブランドを育てたいのに売れるから値引きをする)や、実施後のKPIのすり替え(ex.目的だった商品理解度は上がらなかったけどリーチは多くとれたから素晴らしい施策だと評価する)などといった、発生してはならない事象も起こしかねません。そうすると適切な経営資源の配分が行われなくなってしまいます。また、戦略なき戦術は、思いつくかぎりの「やったほうがよさそうなこと」に追われ、「なぜか忙しいのに成果が思ったように出ない」「とにかく自転車操業なので明日のことが一番重要」といった状況に陥りがちです。
まとめ
リピートは偶然生まれるものではありません。「顧客に何を届けるか」を事実ベースで設計し、「誰のどんな課題を解決するのか」を明確にした企業が、選ばれ続けるのだと思います。
戦術からではなく、事実と戦略をまず見直し、そのためにパーパスとCXから理解することをお勧めします。それが顧客にも企業にも持続的な利益をもたらす、最も堅実な成長戦略と思います。
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
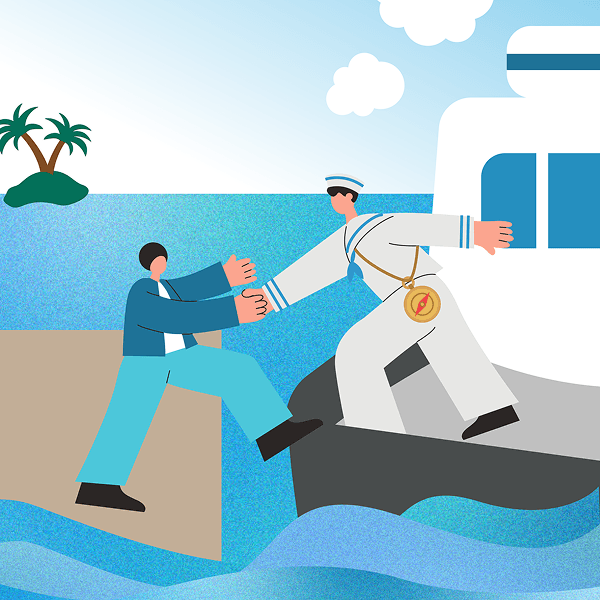
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人
中通 康太
元ネスレ在籍マーケター
大手通販企業でキャリアスタート、ユー・エス・ジェイ、ネスレ日本にてマーケティング部門を歴任する傍ら、Jリーグクラブヴァンフォーレ甲府の事業推進アドバイザーとして活動