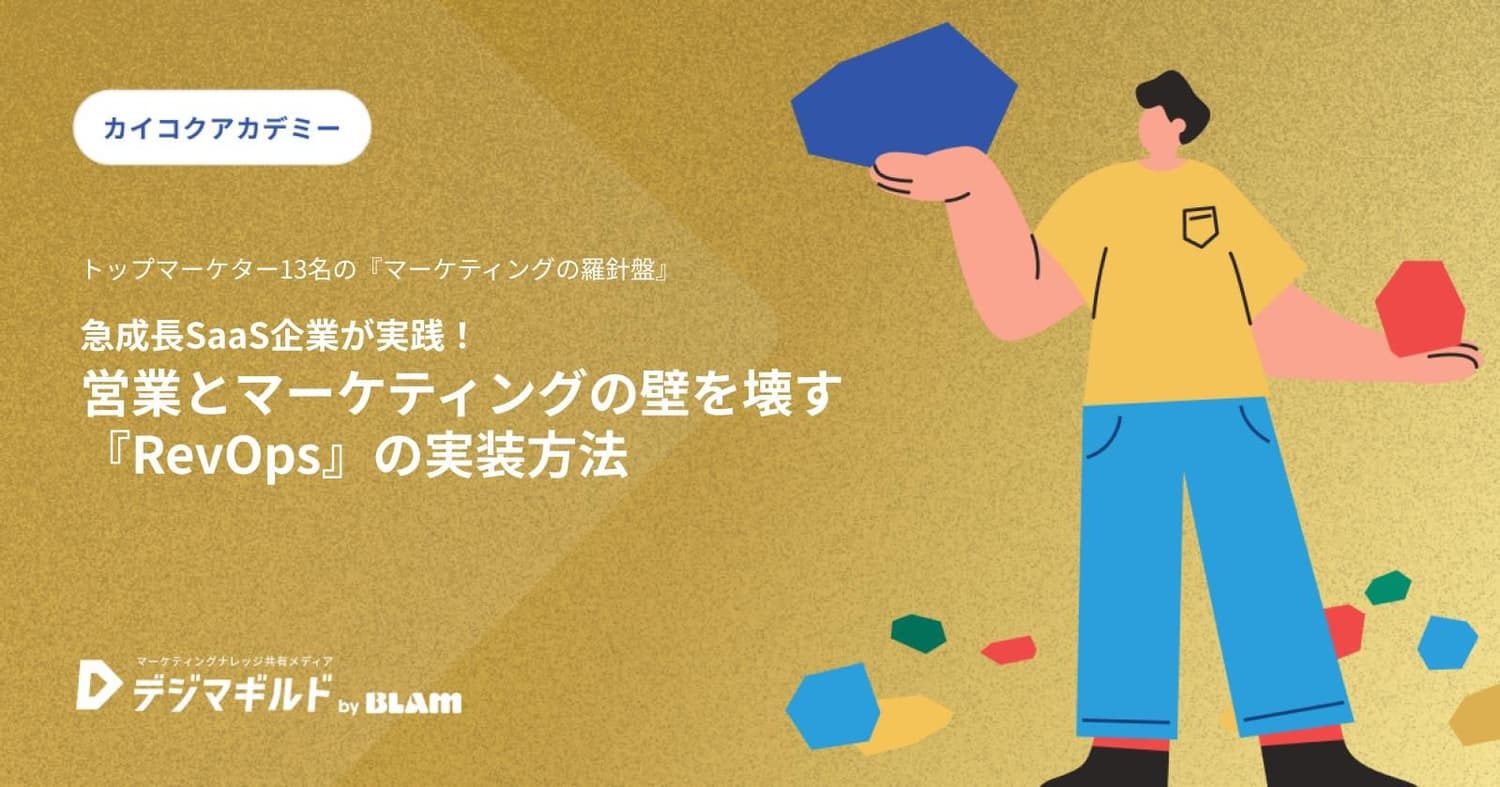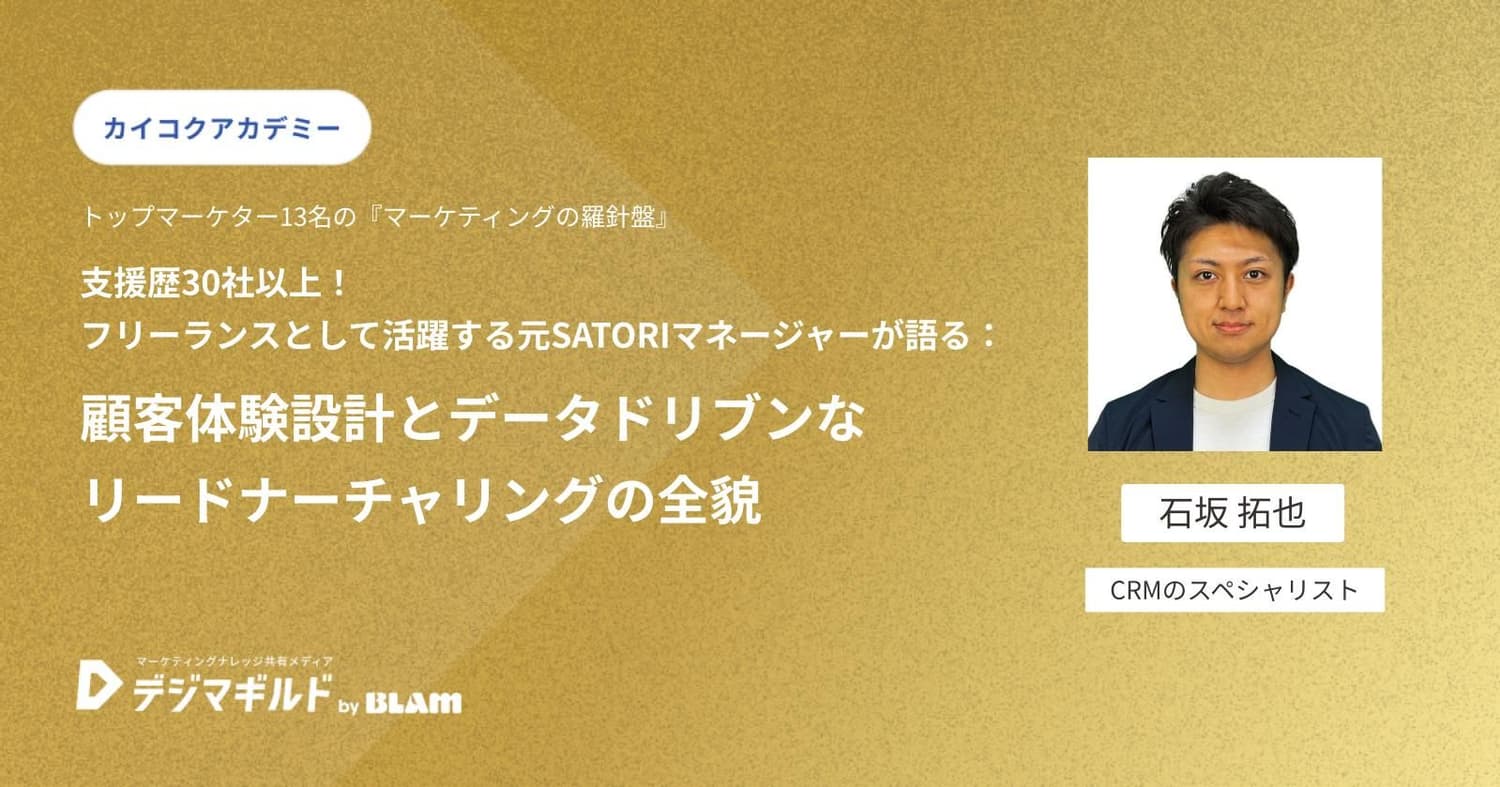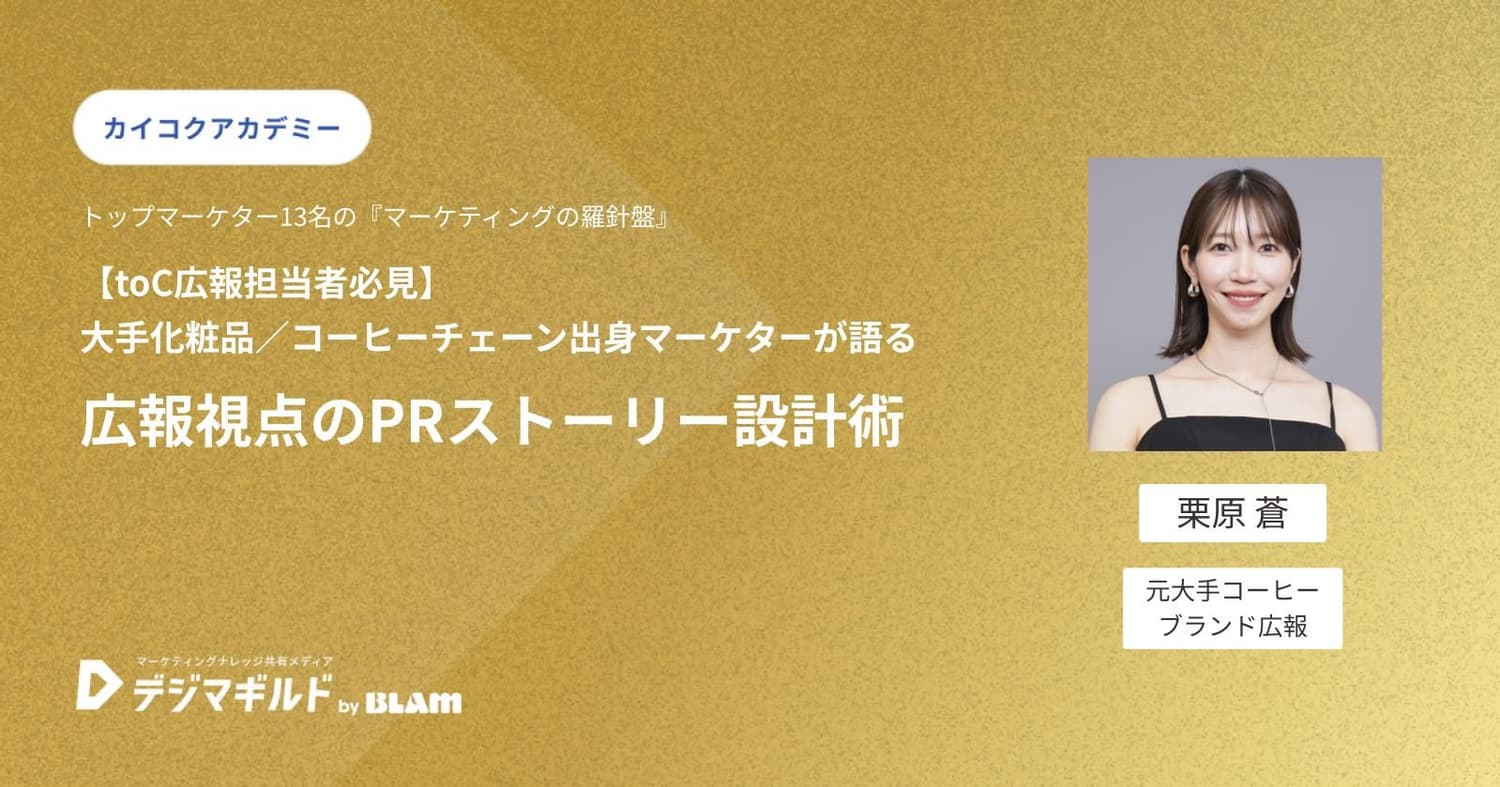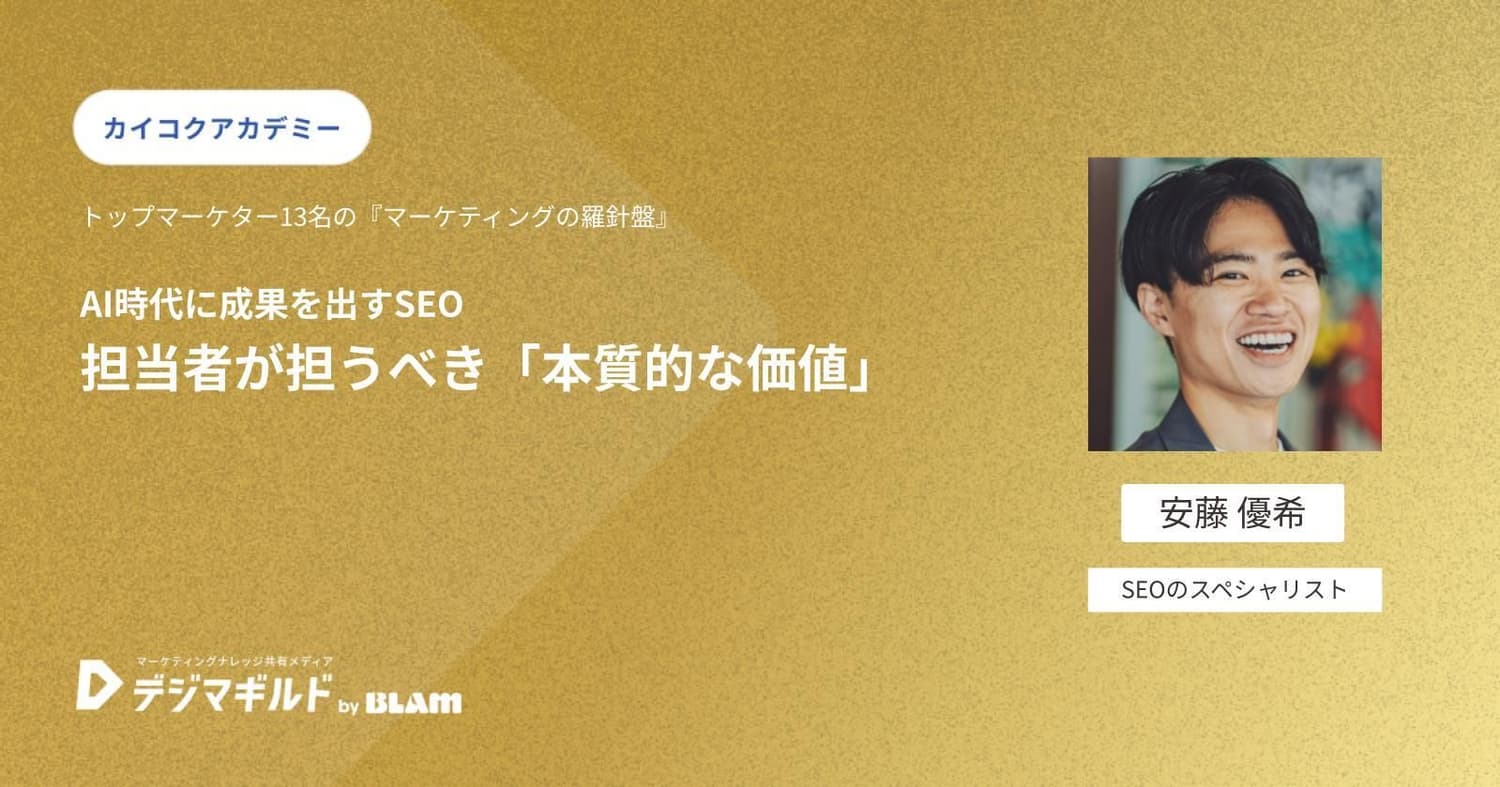
生成AIによってコンテンツを量産できるようになった今、「コンテンツSEOはAIに任せればよい」と考える方も少なくありません。しかし実際に成果を出すには、AIでは生み出せない一次情報やブランドの物語が不可欠です。これからのSEO担当者が担うべき役割は、AIを効率化の加速装置として活用しつつ、人間だからこそ発信できる価値を積み上げること。その舞台となるオウンドメディアの重要性と、具体的な実践法を事例を交えて解説します。
「SEOはもう終わったのでは?」という問いに対して
まず最初に、生成AIの普及を背景に「SEOはもうオワコン」「AIがあれば検索しなくても済む」と考える人も増えてきています。しかしそれは誤解で、これからの時代こそ「良質な情報を持つ者」が選ばれる世界になると考えてます。
1. 生成AIの利用率のリアル
日本国内で生成AIを日常的に使っている人は、まだ 国民の4人に1人程度(約26.7%) にとどまるという調査があります。ターゲットとなる顧客にもよりますが、残りの73.3%と多くの人は依然として検索エンジンを利用しているのが現実です。
2. SEO対策はそのまま LLMO/AIO 対策にもなる
生成AIが返す答えは、Web上の既存情報を再構成したものです。つまり、信頼できる情報を発信し続けることが、AI時代においても参照されるための必須条件となります。
これは裏を返せば、SEOのために質の高い情報を提供し続けることが、そのまま LLMO対策やAIO対策 にも直結するということです。実際Googleの担当者も「AI Overviewにコンテンツを表示するには、通常のSEO対策を講じるだけで十分です。GEOやLLMOなど、他の対策は必要ありません」と言っています。AIに参照される側に立つために、SEOは今も有効なのです。
3. Know系はAIに奪われやすいが、Do系・指名検索は残る
検索されるキーワードや領域によっても傾向は変わります。
- Know(知りたい)系キーワード:一般的な情報やハウツー記事は、AIが即座に回答できるため置き換わりやすい領域です。
- Do(行動したい)系キーワード:予約・購入・申込など「行動の意思」を含む検索は、サービスの詳細情報や商品ページが必要不可欠であり、AIだけでは完結しません。
- ブランド指名検索:サービス名・会社名など固有名詞を含む検索は、AIよりも公式ページや信頼性ある情報源にたどり着きたいニーズが強く、今後も価値を持ち続けます。
生成AIによって検索体験は確かに変化しています。しかし、SEOが完全に不要になることはなく、むしろより本質的な価値を持つ情報発信が問われる時代になったと考えています。
AIで大量生産できる時代、なぜ“人間のSEO”が重要なのか
またChatGPTをはじめとする生成AIの普及によって、コンテンツ制作のハードルは大きく下がりました。キーワードを入力すれば下書きを作成でき、数十本のコンテンツを短期間で制作することも可能です。
しかし、AIに任せきりでコンテンツを量産することには明確なリスクがあります。実際に数百本単位のAIコンテンツを投入した企業で、サイト全体の流入が40%減少した事例も報告されています。考えられる要因は以下の通りです。
- 中身の薄いコンテンツの量産
AI任せのアウトプットは一般化された情報の寄せ集めになりやすく、独自性が欠けてしまう。結果として新規記事が評価されないだけでなく、既存記事の順位まで下落することがある。 - 重複(カニバリゼーション)の発生
構成や表現が似通うため、既存記事と競合し合い、両方の順位を落とす。 - ユーザー体験の悪化
タイトルと本文の不一致、不自然な表現が離脱を招き、CTR・滞在時間・CVRといった指標が軒並み悪化。 - テクニカル面での重複扱い
タイトルやディスクリプションが画一的になり、Googleから重複コンテンツとみなされやすくなる。
こうしたリスクを避けるには、AIを「大量生産ツール」ではなく「アシスタント」と位置づけ、人間が独自情報の投入や品質管理を担うことが欠かせません。
さらに、AIに任せきりのコンテンツは検索結果で上位に表示されにくいのが現実です。理由はシンプルで、Googleが評価基準として掲げる E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性) を満たせないからです。AIは過去の情報を再構成することはできても、新しい経験や独自の視点を生み出すことはできません。
つまり、AI時代におけるSEO担当者の役割は「AIで効率化できる部分」と「人間にしかできない部分」を見極め、適切に組み合わせることにあります。
AIでは代替できない3つの要素
1. 発信者の明確さと信頼性
汎用コンテンツが誰でも作れる時代だからこそ、「誰が言っているのか」は今後より重要になっていきます。記事の著者や運営者を明示し、SNSや外部活動と紐づけることで、Googleにもユーザーにもエンティティとしての信頼性を示せます。
2. 独自データとナレッジの活用
購買データ、予約ログ、ユーザー行動データなど、自社の事業活動から得られる独自の一次情報は、AIには生成できない資産です。これらを素材にすることで「その企業だからこそ発信できるコンテンツ」を作り出すことができます。
3. 体験情報の付加価値
AIは一般論や最適解をまとめることは得意ですが、何かを体験したり経験することはできません。つまり実際にサービスやプロダクトを体験したユーザーの声・口コミ、現場での成功・失敗から得られた学びや経験は人間にしか作り出せないものです。これらを、求めるユーザーに対して適切に伝えることこそ、今後のコンテンツマーケティング・SEOに必要なことだと考えます。
AI時代こそ「オウンドメディア」の価値が高まる理由
こうした「AIでは書けない情報」を発信する場として最適なのが オウンドメディア です。
SNSや広告は短期的な成果にはつながりますが、プラットフォーム依存のリスクがあります。アルゴリズム変更によって突然リーチが減少することも珍しくありません。
一方、オウンドメディアは自社の資産としてコンテンツが蓄積され、SEOによる中長期的な流入源となります。さらに独自データやブランドストーリーを体系的に発信できるため、E-E-A-Tの観点からも評価されやすくなります。
生成AIが普及した今だからこそ、人間にしか作れない情報をオウンドメディアに積み重ね、資産化することが成果を出し続けるカギになるのです。
BLAM社での取り組み事例
このデジマギルドを運営するBLAM社でも「AIに代替できない施策」に取り組んでいるのでご紹介させていただきます。
1. カイコクアカデミーでの知見共有
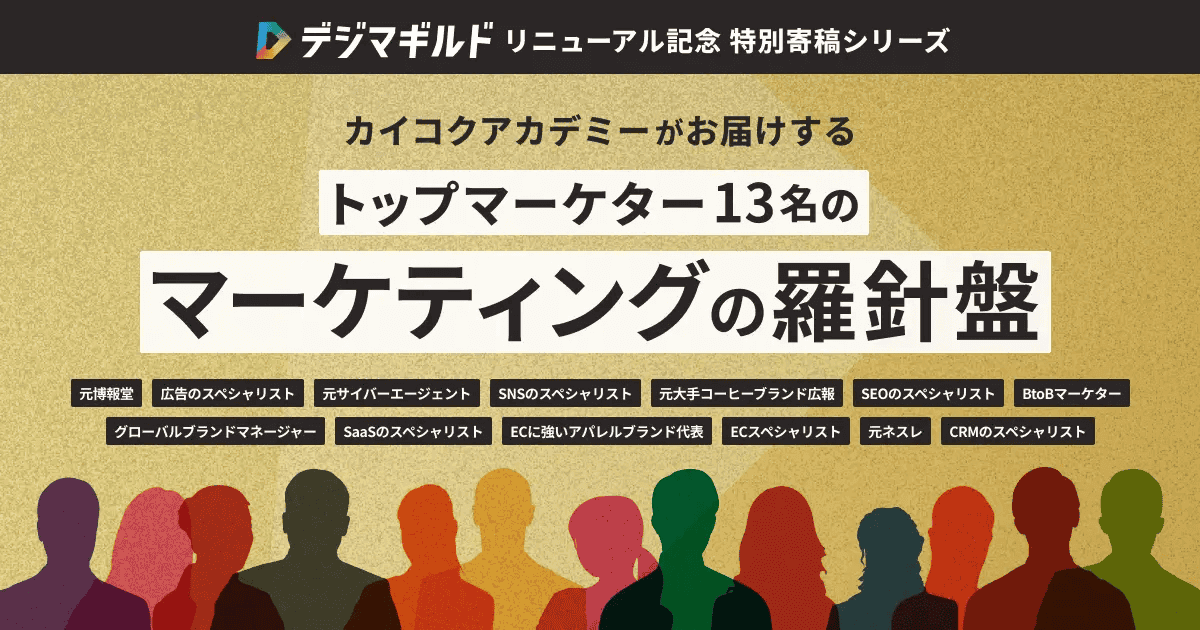
「デジマギルド」の中でも、特にカイコクアカデミーはAIでは再現できない価値を体現しています。
「カイコク」に登録する12,000名以上のプロフェッショナル人材の知見や経験を記事・コンテンツ化して発信する仕組みは、「発信者の明確さと信頼性」「体験情報の付加価値」を抑えた施策になっています。
- 背景:マーケティング現場で積み上げたリアルな知識やノウハウを記事化。
- 特徴:単なる一般論やまとめ記事ではなく、「その人ならではの経験」に基づく具体的な課題解決の指針を提示。
- AIでは代替できない理由:AIは情報を整理することはできても、専門家の一次経験や現場のナレッジは生成できない。
実際に、デジマギルドは流入数・問い合わせ数ともに上昇傾向にあり、こうした「自社独自のアセット活かす取り組み」が成果につながることを実感しています。
2. BLAM社顧客の導入事例

BLAM社は顧客事例の公開にも積極的に取り組んでいますが、これもAIでは生成不可能な「一次情報の活用」です。
- 背景:複業マッチングサービス「カイコク」や外部のプロフェッショナル人材を柔軟に組み合わせ、最適なプロジェクトチームを組成する「PjTO(Project Team Optimization)マーケティング」などの手法を通じて、顧客の事業成長を支援。実際の支援内容やその成果をインタビュー形式で記事化。
- 特徴:顧客が抱えていた課題、それに対する具体的な取り組み、成果の数値や学びをストーリー化。
- AIでは代替できない理由:顧客とのリアルなやり取りや成果データは自社にしか存在せず、AIでは作れない唯一無二の資産。
「顧客の声」をベースにしたコンテンツは、見込み顧客に対して信頼性を与えるだけでなく、SEO的にも評価されやすい構造になっています。
上記のBLAM社の取り組みは、AIに代替できないオリジナルコンテンツがSEOと事業成長を両立させることを示しています。
私自身が経営するHabiny社でも20社以上のオウンドメディア支援を行っていますが、オリジナルコンテンツをしっかり作り込んでいるサイト は中長期的に流入数やコンバージョン数を維持・上昇させているのに対して、汎用的なまとめに終始しているサイトは中期的に下落傾向があるように感じています。
つまり、BLAM社が実践しているように「AIでは生み出せない独自のコンテンツを積み重ねる」ことこそが、AI時代のSEOにおける競争優位を築く本質的な取り組みなのです。
隠れた「資産」を見つけて発信することが、AI時代のSEO・コンテンツマーケティングの成果に繋がる
AIはコンテンツ制作を加速させる強力なツールですが、それだけでは成果は出ません。検索エンジンやユーザーが求めるのは、独自データや体験情報など人間にしか発信できない価値です。
実際、多くの企業が「自分たちには発信できるネタが少ない」と感じていますが、目線を変えると社内には多くの“隠れた資産”が眠っています。
- 顧客とのやり取り:営業やカスタマーサポートの会話ログ、問い合わせの傾向
- 社内に蓄積された知見:定例会議の議事録、業務改善の工夫、独自のフレームワーク
- 自社サービスの利用データ:購買履歴、アクセスデータ、ユーザーの行動特性
- 社員個人の体験談:導入プロジェクトの成功/失敗談、現場での判断や工夫
これらは外部からは入手できない情報であり、AIが模倣することもできません。言い換えると、“人間が体験したこと”や“事業活動で蓄積されたこと”を見つけ出すこと自体が競争優位の源泉になります。
担当者の方は、自社で「AIでは作れない情報」を棚卸しすることからぜひ始めてみてください。普段何気なく接している顧客データ、社員の声、調査結果などが、編集・整理してコンテンツに落とし込むことで強力な資産に変わります。
さらに、それらをオウンドメディア上に蓄積し、SEOだけでなく採用やPRにも横展開することで、企業ブランド全体の価値を底上げする効果が期待できます。
👉 この記事の内容が気になった方は、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。
御社の「隠れた資産」を発掘し、成果につながるオウンドメディア・SEO戦略にご一緒できればと思います。
この記事を書いた人
安藤 優希
経歴
早稲田大学卒業後、グリー株式会社に入社。
社内新規事業としておでかけメディア「aumo」を立ち上げた後、法人化。設立時に取締役に就任し、その後代表取締役に就任。メディアは国内最大級の1700万MAU規模まで成長、メディア基盤を活かして飲食店・ホテル向けのSaaS事業を立ち上げ、リリース後3年で3万5000店舗に導入。
2024年10月 株式会社Habinyを設立。地域・地方企業を中心としたDX支援事業などを展開中。
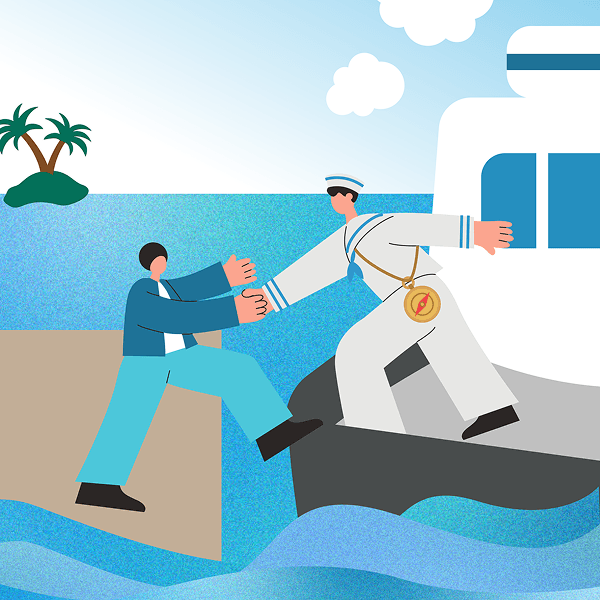
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。