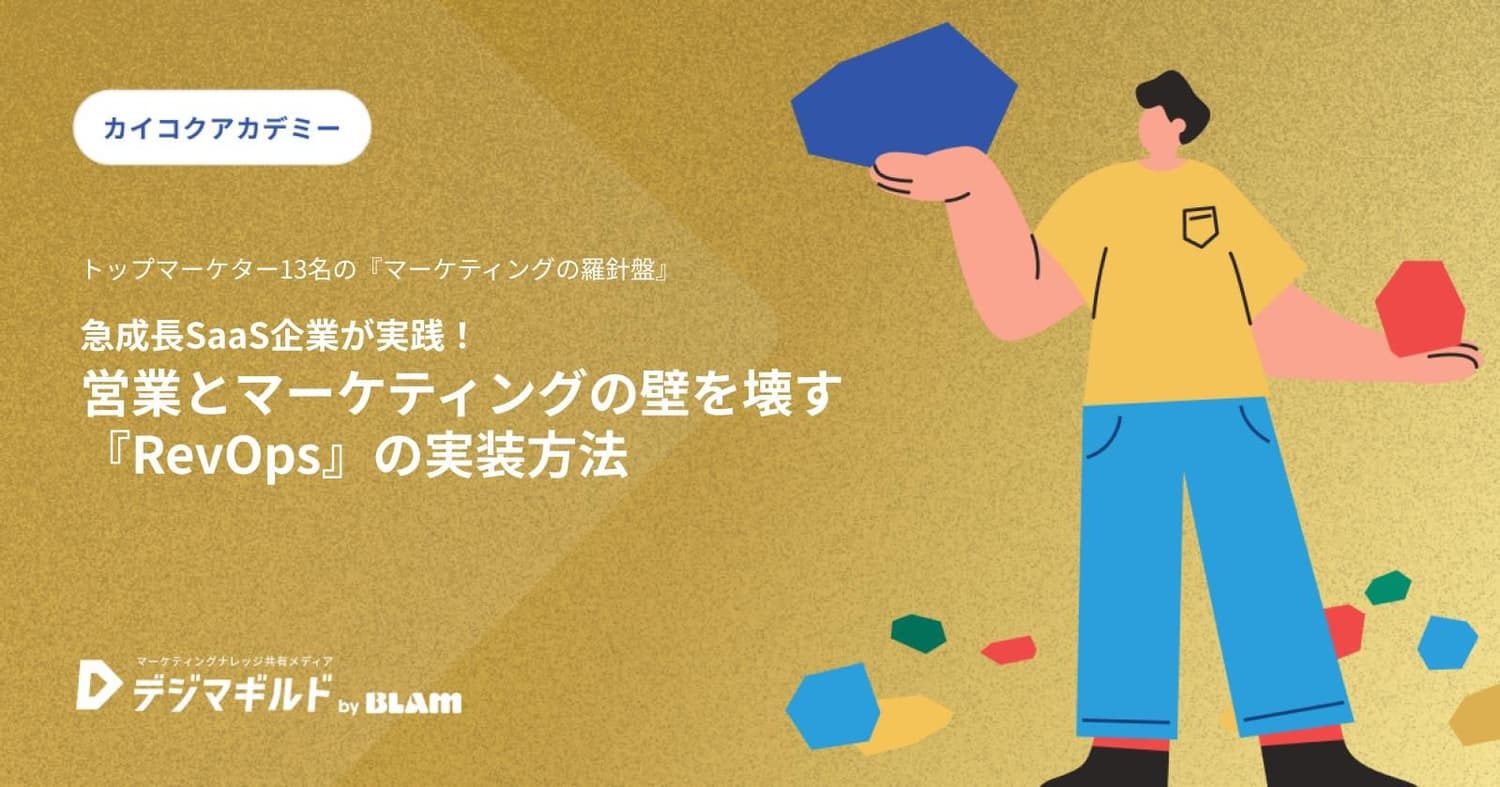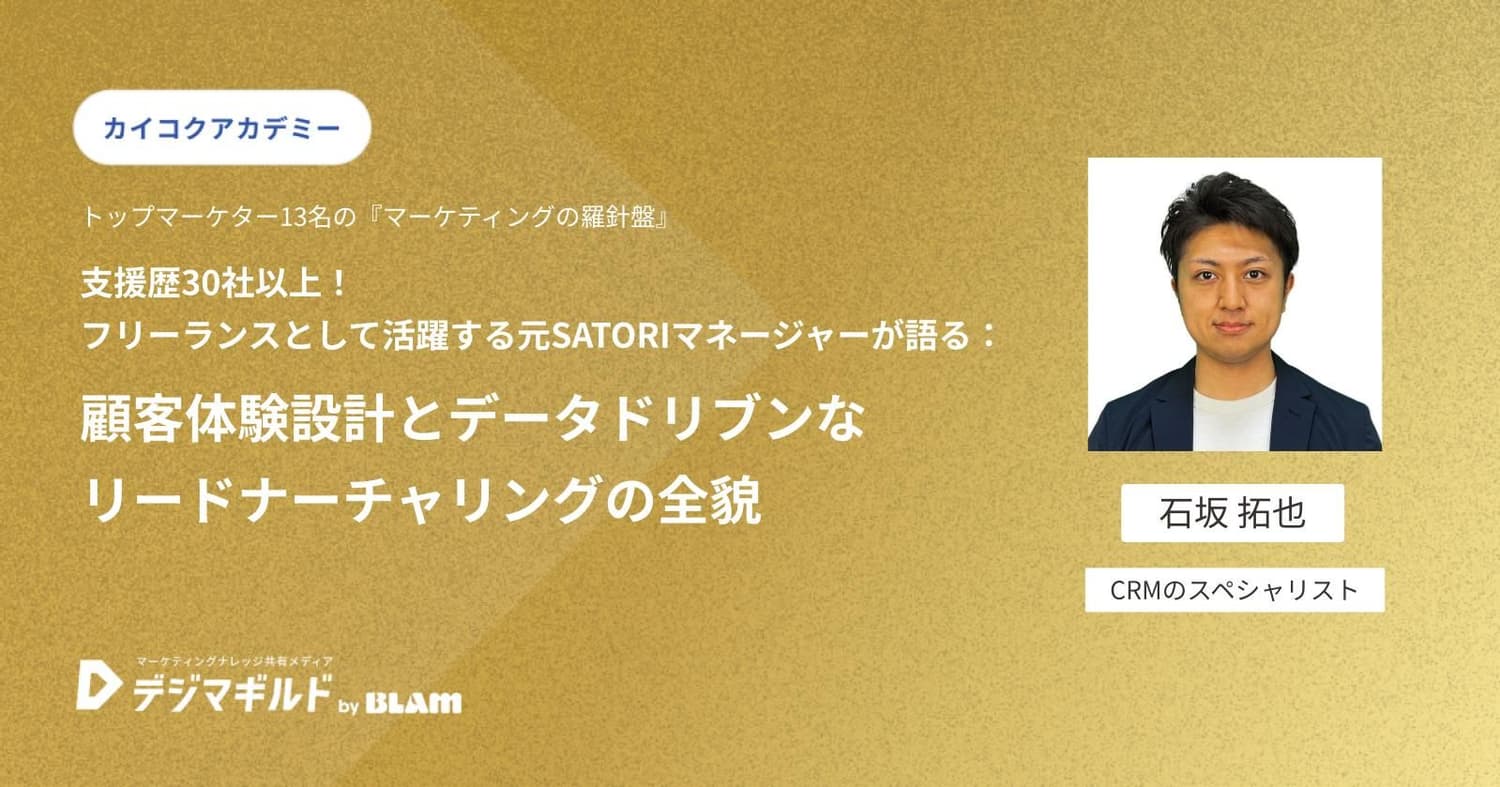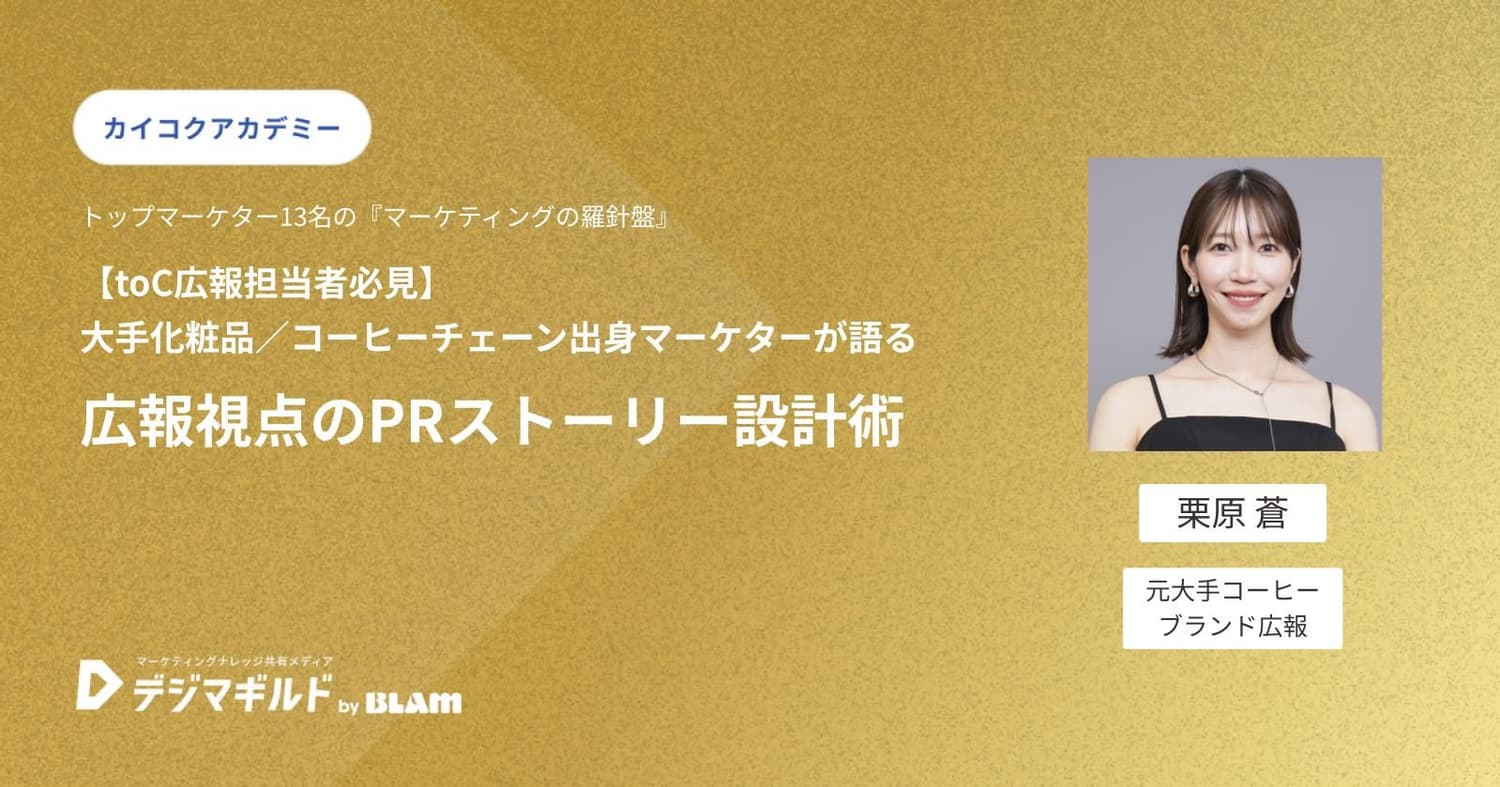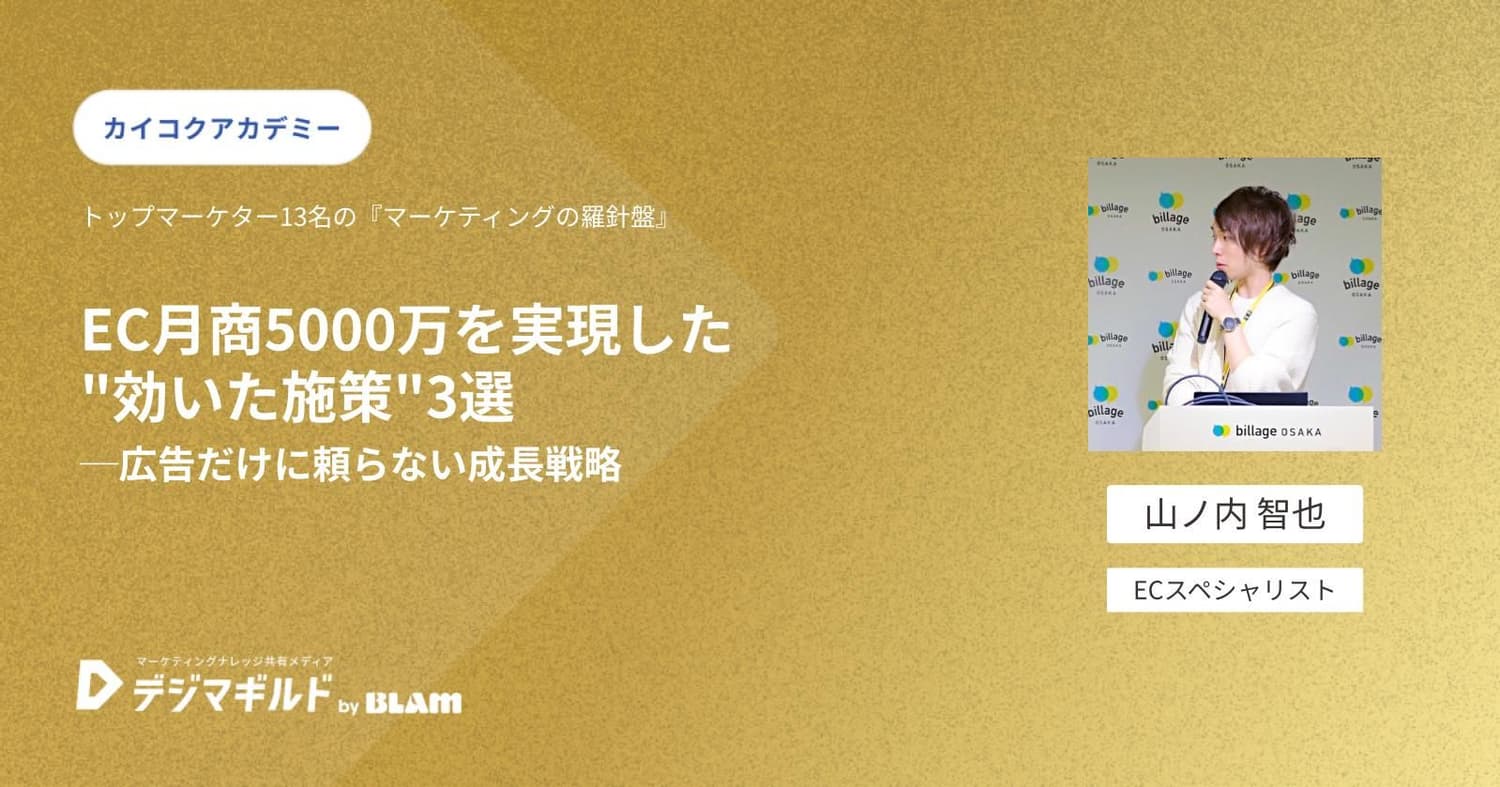
はじめまして。マーケティング歴12年の山ノ内と申します。
2013年よりレディースアパレルECサイト「Pierrot」のCMOとして、自社サイトを中心に、楽天・Yahoo!ショッピングなどのモール運営全般に従事してきました。
特に自社サイトでは立ち上げから携わり、5年で月商5,000万円規模まで成長させました。
現在は独立し、企業様のマーケティング支援を行う傍ら、自社ECサイトやメディアの運営にも携わっています。現場での試行錯誤や成果事例を活かし、リアルな視点で支援できるのが私の強みです。
今回は、これまで多数のEC運営に携わってきた経験から、「広告だけに頼らずに売上を伸ばした」施策から特に"効いた"ものを3つ厳選してご紹介します。
が
課題解決をサポート!
広告だけでは限界が来る、次の一手とは?
ここ数年で、EC業界を取り巻く広告環境は厳しさを増しています。リスティングやSNS広告のCPA(顧客獲得単価)は年々高騰し、「広告を回せば売れる」時代は終わりを迎えつつあります。
実際、私のもとにも「広告に頼ってきたけれど売上が頭打ち」「一時的には売れるがリピートにつながらない」といった相談も増えています。
支援先でも自分自身の経験でも、立ち上げフェーズから月商100万円・300万円・500万円・1,000万円・5,000万円と売上を積み上げていく各フェーズの中で、広告だけでは乗り越えられない壁が何度もありました。
だからこそ、広告だけに依存せず、ECサイトの総合的な"地力"を育てていく施策に注力することで打破できました。
もちろん、すぐに効果が出るものばかりではありません。ただ、正しい形で丁寧に積み重ねていけば、確実に売上の土台となり、長期的な成長につながります。
今回は、どのフェーズの事業者にも取り組んでいただきやすく、かつ再現性の高かった「地力を育てる3つの施策」についてお伝えします。
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
施策①:オウンドメディア設計(SEO集客)
広告やSNSのように"届ける"手段と異なり、オウンドメディアは「ユーザー自らが検索してやってくる」能動的な流入経路です。
だからこそ、ただ記事を書くのではなく、検索する人の意図やニーズにしっかり寄り添ったコンテンツ設計が求められます。
私が支援や自社で実践してきた流れとしては、たとえばWordPressやブログ機能、楽天であればコンテンツページ機能などを活用し、検索ニーズに合わせた記事を制作。
SEOで上位表示を狙い、そこから集客・購買につなげるというものです。
顧客に"比較検討される"立場をどう築くか?
まずは、自社ブランドや商品を「知ってもらう」ことがスタートラインです。
特にオウンドメディアは、何かしらの疑問や悩みを持って検索してきたユーザーと初めて接点を持てるタッチポイント。つまり、認知を獲得するための受け皿として機能しやすい施策です。
検索行動の背後には、必ず「知りたい理由=検索ニーズ」が存在しています。
たとえば「着やせする方法」で検索する人は、
- 最近太って見える気がする
- 体型が目立たない服の選び方を知りたい
- 細見えする着こなし方が知りたい
などの悩みや目的を持っており、何かしらの具体的なヒントや回答を探して情報収集しています。
こうしたニーズに対して、
- どんな色や形を選ぶとすっきり見えるか
- スタイリングの工夫でどんな変化があるか
- その悩みを自社商品でどう解決できるか
といった情報を「悩み→理由→解決策→商品紹介」という流れで整理しながら提供すると、「なるほど、この商品なら着やせできそう」「このブランドって私の体型に合うかも」といった納得感を持ってもらうことができます。
コンテンツから購入につなげる導線設計
よくある失敗は、「アクセスは集まっているけど全く売れない」というケースです。これは、検索ニーズには答えているけれど、商品との関連性や導線が弱いパターンです。
ECの売上につなげるコンテンツとして、重要なポイントは以下です。
- 疑問や悩みを「商品」で解決できているか?
- なぜその商品が解決策になりうるのか、きちんと「主張」できているか?
- その主張に「納得感」があるか?
上記の点を押さえることで、コンテンツと商品の接続が自然になり、購買にもつながりやすくなります。
「お悩み→解決→商品提案」というストーリーラインを一貫させることで、SEO経由からの売上貢献にしっかりとつながっていきます。
伸びる記事の4条件
私がこれまで多くのオウンドメディアやSEO記事を制作・支援してきた中で、「伸びる記事」にはいくつかの共通点があります。
PVが取れるだけでなく、きちんと売上に繋がる“強い記事”に共通するのは、以下の4つの条件です。
- ユーザーの疑問や悩み(=検索ニーズ)を明確に捉えているか
→どんな人が、どんな目的で、どんな状況でそのキーワードを検索しているのかを言語化できているか。 - そのニーズに対する回答がズレなく的確であるか
→検索意図に対して"ドンピシャ"で答えており、読者に「それそれ!」と思ってもらえる内容になっているか。 - 悩みを「商品」で自然に解決できているか
→記事の流れの中で、違和感なく自社商品を解決手段として提示できているか。 - その商品である理由(=主張)が明確で、かつ読者に納得感があるか
→たとえば「着やせに効くアイテム」といっても、ワンピースを推すのか、ボトムスを推すのか、何を軸に選ぶのかは提案者次第です。
そこに一貫した主張があるかどうか。また、その主張に対して「確かにそれなら合いそう」「自分にも当てはまりそう」と読者が納得できるかどうかも重要なポイントです。
この4点がしっかり揃っている記事は、検索順位も安定しやすく、読了後のアクション(CV)にも繋がりやすい。いわば"読み応えのある売れる記事"になります。
施策②:SNS・インフルエンサー施策
SNSは、ユーザーの"共感"を生み、興味関心を喚起するために非常に有効なチャネルです。
前提として、それぞれのSNSには異なる特性があり、自社商材との相性を見極めることが重要です。
ここでは特に支援先で活用が多いInstagramを例に取り上げ、運用設計の考え方と、成果につながるインフルエンサー施策について解説します。
自社SNS運用設計における3つの基本姿勢
SNS運用でまず意識すべきポイントは、以下の3つです。
- フォロワー数ではなく、"エンゲージメント(いいね・保存・コメント等)"を追う
- 商品紹介ではなく、ユーザーに寄り添う"コンテンツ"を届ける
- 実際の店舗で接客するように、"双方向コミュニケーション"を意識する
なぜこの3つが重要かというと、SNSは売る場というよりも「関係構築をするための場所」の側面が強いからです。
たとえば、Instagramでは10万フォロワーいてもストーリーズの閲覧が数件というアカウントも非常に多いです。
これは「アクティブなユーザー」が少ない状態で、見た目の数字だけが先行してしまっている典型例です。
また、「この商品おすすめです!」といった直接的な商品紹介投稿は、"売り感"が前面に出てしまい、売り感を感じた瞬間にユーザーは一気に冷めてしまいます。
結果としてエンゲージメントが下がり、リーチも悪化していくという悪循環になります。
実店舗での接客と同じで、まずはファーストアプローチでお客様の悩みやニーズをヒアリングしつつ、それに対して提案する。この流れや順序をSNS上でも再現することで、自然と商品にも関心を持ってもらえるようになっていきます。
つまり、SNSで発信すべきは「商品情報」ではなく「ユーザー視点での気づきや解決のヒント」。それこそがコンテンツであり、その先に商品紹介があるという順序が大切です。
インフルエンサー施策が成功する3つの要素
インフルエンサーを起用する際も、単なる「フォロワー数」で選定すると失敗するケースが非常に多いです。
以下の3つの視点での評価が成果に直結します。
1.本当に影響力があるかどうか(=ファンの有無)
フォロワー数が多くても、実際に買いたいと思ってくれるファンがいなければ意味がありません。
判断基準としては、インサイトデータを確認するのが理想ですが、それが難しい場合は投稿ごとのコメント内容を見て判断します。
「かわいい」「似合ってる」といった表層的なコメントよりも、「どこで買えますか?」「それどこのですか?」などいった購買意欲の高い反応があるかをチェックします。
2.自社商品との相性
同じインフルエンサーでも、A社では売れたのにB社では全く売れないということはよくあります。
商品の世界観や価格帯、フォロワー層とのマッチ度が鍵です。
ここは実際に何人かと組んでみないとわからない部分もあるので、定期的なテストと検証(PDCA)が必須となります。
3.投稿時の熱量やモチベーション
インフルエンサー施策の成否を分ける大きな要因のひとつが、「その投稿にどれだけ熱量が込められているか」です。
案件色の強い"こなしているだけ"の投稿では、ユーザー側も敏感に違和感を覚え、反応が一気に鈍くなります。
一方で、「この商品、本当に気に入っていて普段から使っています」「このブランド、ずっと好きで応援してます」といった"本音の熱量"が感じられる投稿は、共感や購買行動につながる可能性がぐっと高まります。
この熱量を引き出すためには、単に依頼して終わるのではなく、インフルエンサーと丁寧に関係を築いていくことが大切です。
たとえば、初回投稿だけで完結せず、2回目・3回目と継続的に依頼していくこと。
さらに、そのやり取りの中で相手の投稿内容や世界観にしっかりと目を通し、興味やリスペクトを持って接すること。
加えて、こちらのブランドの想いや背景を一方的に伝えるのではなく、相手のスタイルや意向も丁寧に汲み取るような、「人対人」の双方向のコミュニケーションを大切にする姿勢が、信頼関係の構築につながり、結果として投稿の熱量や成果にも直結してきます。
「仲の良い友達から頼まれたから紹介したくなる」
そんな空気感を、仕事の中でも自然につくれると、インフルエンサーの投稿にもそれがにじみ出てきます。
中長期的にファンを増やすSNSの全体設計
インフルエンサーを通じてブランドや商品に興味を持ってもらい、購入体験を経てブランドに好感を抱いてもらう。そのうえでアカウントをフォローし、自社アカウントの投稿で継続的な関心を引き続ける。
この流れが構築できると、SNSは単なる告知ツールではなく、「ブランドのファンを育てる場」に進化します。
SNS・インフルエンサー施策は、売上の瞬間的な上昇だけでなく、支持され続けるブランドになるための土台にもなるのです。
施策③:CRMとLTV最大化による売上の底上げ
どれだけ広告で新規顧客を獲得できたとしても、リピート購入につながらなければ、事業はいつまでも「広告を回し続けないと売上が立たない状態」から抜け出せません。
広告費の高騰が続く今、中長期的な利益の安定化を目指すうえで、CRM(顧客関係管理)とLTV(顧客生涯価値)の最大化は避けて通れないテーマです。
私自身の経験としても、またこれまでご支援してきた多くのEC企業様でも「広告中心に売上を上げているものの、その後が続かない」「リピート購入につながりにくい」といった課題感をたくさん見てきました。
この"次の壁"をどう乗り越えるかが、事業の安定成長に向けた大きなターニングポイントになります。
今回は、私自身も実践してきて、かつ支援先でも成果につながってきたアプローチを3つに整理してご紹介します。
が
プロをマッチング!
1.LTVの把握からはじめる
まず着手したいのは「現状のLTVをきちんと可視化すること」です。
リピート率は出しているけれど、LTVまでは整理できていないという企業様は意外と多いです。
実際にLTVの算出やモニタリングの仕組みを整えると、「こんなに単価が低かったのか…」「こんなに定着していなかったのか」と、思っていた現状とのギャップに気づかれることも少なくありません。
このLTVの見える化ができると、広告施策のKPI設計の精度も一段上がり、「何円まで獲得単価を許容できるか」「もっと広告を踏めるな」などの具体的な判断ができるようになります。
2.LINE・メルマガの設計で売上を底上げ
CRM施策のなかでも、成果に直結しやすいのがLINEやメルマガの配信設計です。ここで意識したいのは、以下の3点です。
(1)接点の最大化
「LINEは週に何通までが適切か?」「メルマガは毎日送っても大丈夫か?」
これは非常によくある質問ですが、私の考えとしては「配信できるならできるだけ配信すべき」です。
もちろん、内容によっては配信解除が発生することもありますが、それよりも重要なのは、解除せずに読んでくれる"ファン層"との接点をどれだけ保てるかです。
たとえばメルマガは1日1通、LINEは週1~2通でも問題なく運用できます。
そのうえで、「読者が飽きずに、開封したくなる内容」「欲しい情報をしっかり届ける」工夫をすれば、配信解除率は低く抑えることができます。
(2)リスト獲得の最適化
リスト獲得の最適化も非常に重要なポイントです。
多くの企業様で「LINEやメルマガのバナーは設置しているのに、なかなか登録が増えない」とご相談を受けますが、よく見ると以下のような改善余地があるケースが多いです:
- 登録導線が埋もれている(=露出不足)
- 訴求文や特典が弱く、登録メリットが伝わっていない
- 「今すぐ登録すべき理由(=緊急性)」がない
- タイミングや出し方がユーザー心理とズレている
これらは少しの改善で反応が大きく変わることも多く、登録率が一気に伸びた事例も少なくありません。
(3)ステップ配信の構築
単発配信だけでなく、ステップ配信を構築することで、全体のリピート率が底上げされたケースは数多くあります。
たとえば、もともとリピート率15%前後だったECサイトで、購入後のステップ配信(初回購入・2回目購入・離脱リカバリーなど)を丁寧に設計したところ、1年後にはリピート率が約30%へと倍増した事例もあります。
ここでのポイントは、「ステップ配信自体をまず構築すること」と「購入回数やユーザー属性ごとに配信内容やタイミングを設計すること」の2点です。
とくにステップ配信の構築については、心理的なハードルの高さや一定の工数がかかることから、未着手の企業も少なくありません。
しかし、一度しっかりと構築してしまえば、その後は自動で売上を生み出してくれる資産として機能し、手間をかけずにLTVの底上げを図ることができます。
このように、
「LTVの可視化 → 接点の最適化 → 自動化(ステップ配信)」
という順番で整備していくことで、広告だけに依存しない強い顧客基盤を築いていけます。
結果として、売上の変動幅が小さくなり、利益面でも安定化が図れるようになっていきます。
応用編:3施策をどう組み合わせれば売上はさらに加速するか?
ECの売上を継続的に伸ばしていくうえで鍵となるのは、「ユーザーの可処分時間をどれだけ自社に割いてもらえるか」という視点です。
オウンドメディア、SNS、CRM、これらすべての施策は、突き詰めれば「ユーザーにどれだけ長く、深く、自社やブランドに接触してもらえるか」に集約されます。
各施策を連携させることで、効果は掛け算になる
それぞれの施策は、以下のような主な役割を担います。
- SNS:興味関心層への認知獲得・共感形成
- オウンドメディア:比較検討層への理解促進
- CRM(LINEやメルマガ): 既存顧客との関係継続・LTV最大化
ただし、役割はこれだけにとどまりません。
たとえばSNSはファン化によってリピート促進にもつながり、CRM施策も初回購入の後押しを担うことがあります。
さらに、オウンドメディアで制作したコンテンツを各SNSやメルマガに横展開することで、情報発信を"点"から"面"に広げることができ、各施策が連動して成果を押し上げる構造をつくることが可能です。
こうした各施策をバラバラに取り組むのではなく、相互に連動させることで、ユーザーとの接点が広がり、ブランドへの接触頻度や滞在時間も増えます。
結果として、認知・検討・購入・リピートといった一連の購買行動を、自然な流れで促すことができ、売上の伸びを加速させる原動力になります。
どのフェーズのECでも再現可能な仕組みになる
今回ご紹介した3つの施策は、どれも私自身が実際に運営してきたECでも、複数の支援先企業でも成果を出してきた再現性のある施策です。
もし、この記事を読んで「この部分は未着手だった」「やってはいるけど成果が出ていない」と感じた部分があれば、ぜひ一度立ち止まって見直してみてください。
また、記事内ではなるべく噛み砕いてお伝えしたつもりですが、実際には各施策の中にもっと細かなノウハウやチェックポイントが存在します。
「実際に自社に落とし込むにはどう進めればいいのか分からない」
「社内に実行できる人材がいない」
そんなときは、無理に一人で抱え込まず、各分野に強いプロのマーケターの力を借りて進めるのも有効な選択肢です。
伴走型で進めることで、戦略設計から運用までをスムーズに進行でき、成果にもつながりやすくなります。
広告に依存したEC運営から一歩抜け出したい方は、今回ご紹介した各施策をぜひ自社に合わせて取り入れてみてください。
「やってみたい」と思えた施策があれば、小さくでも一歩踏み出すことで、大きな変化につながります。
外注か採用か迷ったら
へ相談!
この記事を書いた人
山ノ内 智也
ECスペシャリスト
マーケティング歴12年。過去ECサイト立ち上げから5年で月商5000万規模にグロース、メディアは1年半で160万PVにグロース、セミナー登壇実績等。特に自社EC・楽天や他モールの多品目系ECサイトが得意。現在は企業様へのマーケティング支援・自社EC運営・メディア運営等幅広く活動中。
リンク掲載:
会社HP:
PerCoRe合同会社
https://percore.co.jp/
運営ECサイト:
大人のための高見えアクセサリーブランド「ChooMia(チュミア)」
https://choomia.com/
運営メディア:
【プチ研】プチプラファッション研究所
https://putiken.jp/
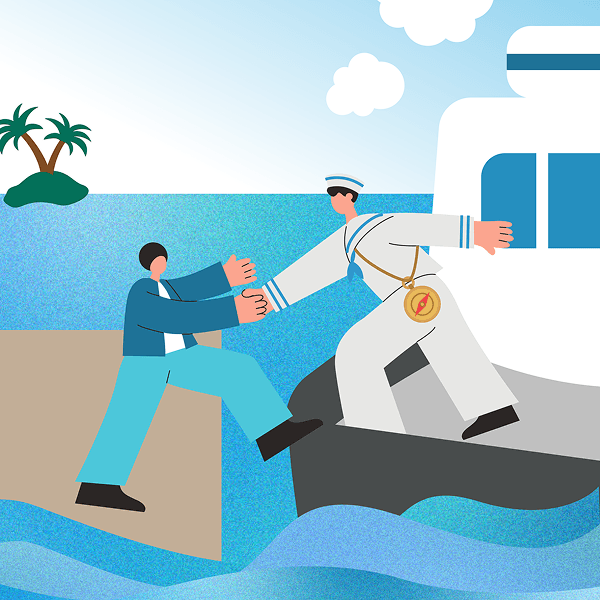
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。