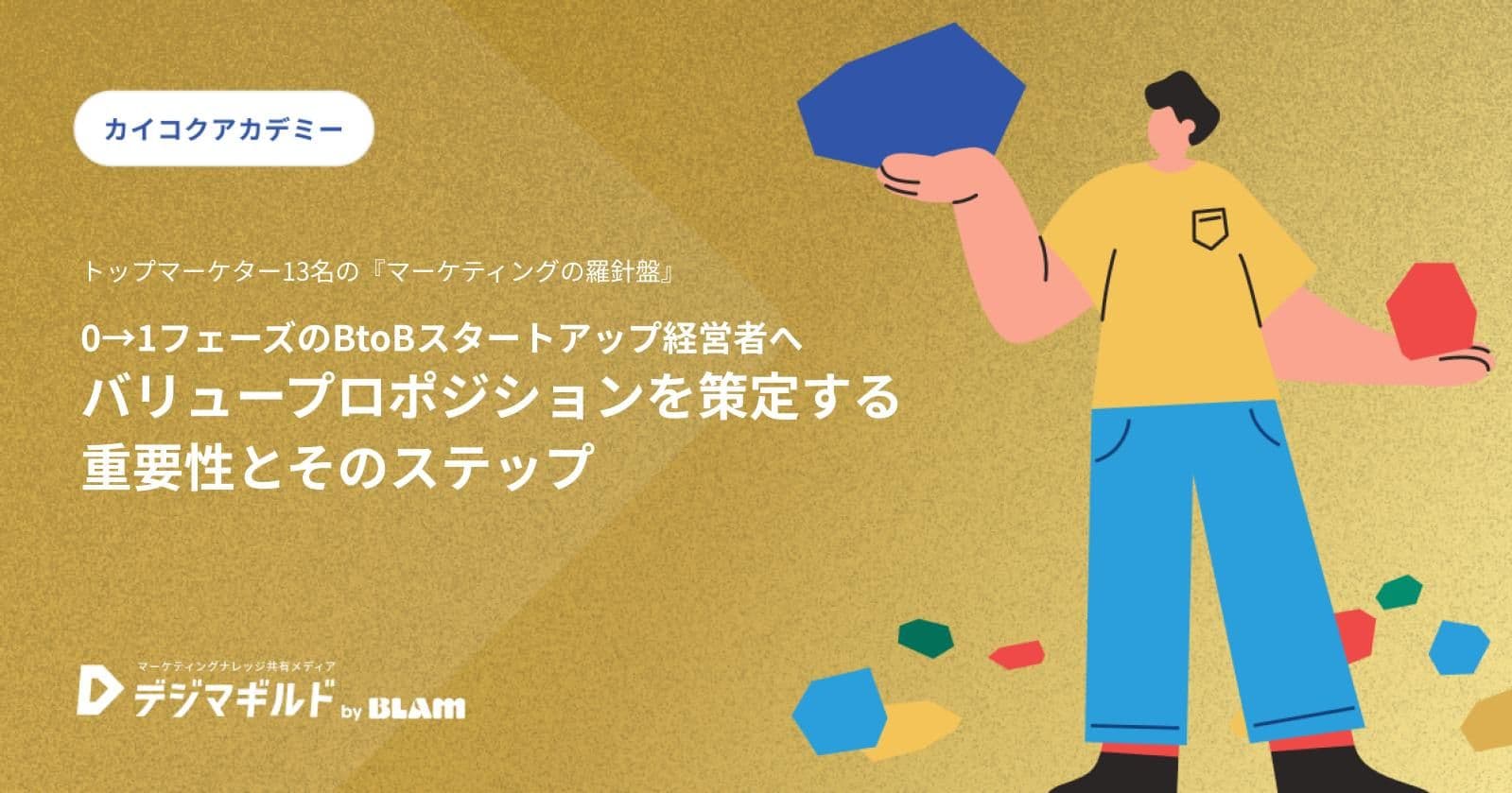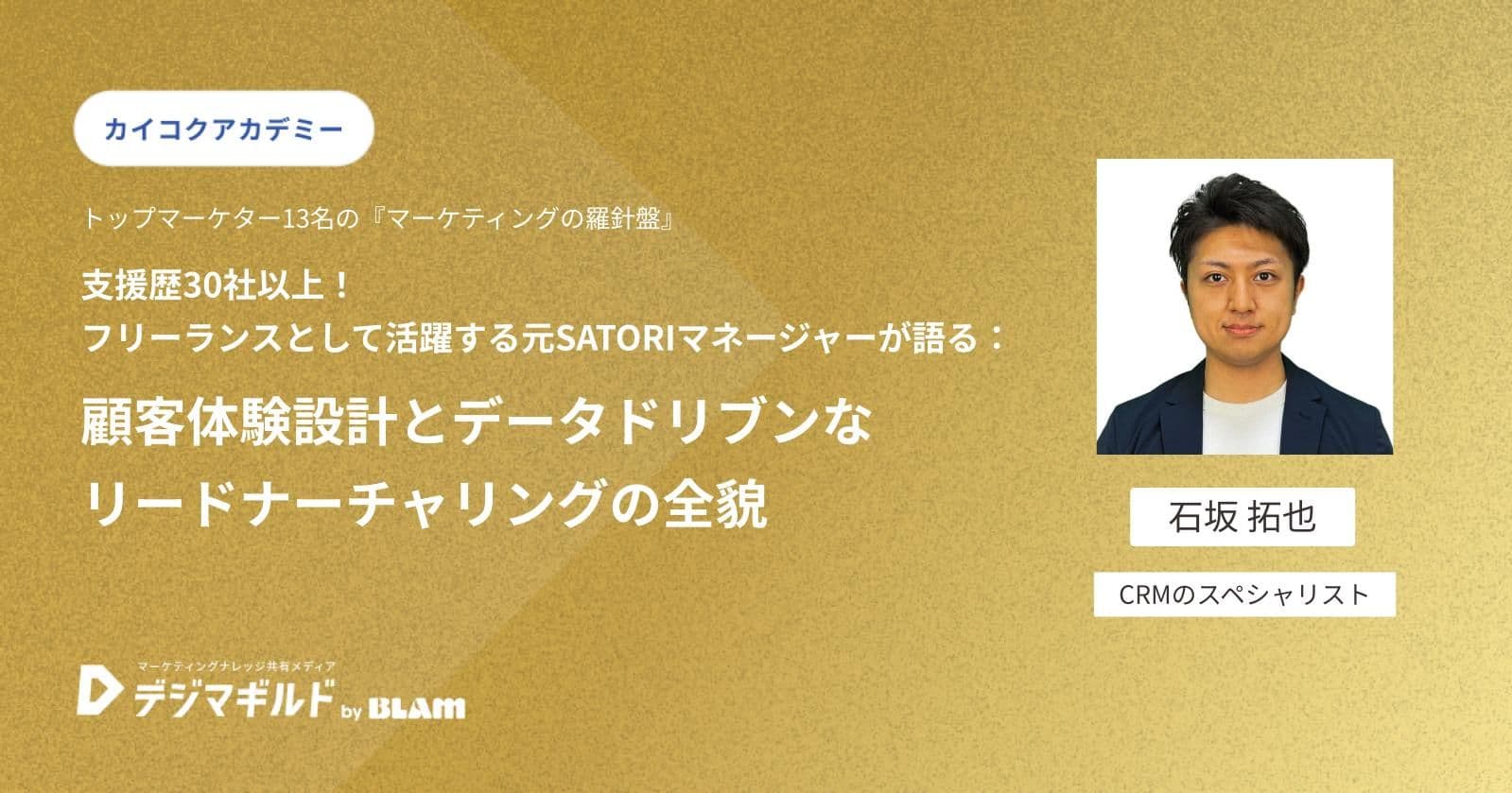1章:グローバルブランドが今、立ち返るべき原点
「グローバルブランドで働く以上、フレームが決まっている中でのローカライズしかできない」
10年以上外資系消費財メーカーでマーケティングに携わってきた私の周りでも、多くの同じような声を聞いてきました。
しかし、マーケターの皆様には言わずもがな、各国・各市場で、消費者の価値観・ニーズ・行動は大きく異なり、“一律の正解”など存在しません。
私も複数の外資系メーカーのビジネスサイズの大きなブランドを歴任する中で、この“理想と現実”のギャップに幾度となく直面してきました。
グローバル本社から提示されるグローバル戦略は、優れた構想でありながら、日本の消費者にそのまま響くとは限らない。
そのときに何を拠り所にすべきか――答えは明確でした。
現職でも声高に叫ばれる「Consumer is boss」=すべてはお客様起点で考えること。
全てのフェーズでこの信念に立ち返り、「我々のブランドは、商品は、対峙している日本のお客様に対して、どのような付加価値を提供できるのか?」を問い続けること、そして、実際のブランドのアクションとしてお客様にどう還元できるのかを考え行動することこそが、全ての解だと考えております。
本記事では、グローバルブランドの成長を担うブランドマネージャーやマーケターに向けて、
“消費者起点”のマーケティングがいかに市場を動かし、実際の価値を生み出すのかを、実体験に基づいてお伝えします。
2章:ローカルアダプテーションの在り方
さて、最初にグローバル戦略・プランがそのままでは通用しないのかを改めて確認してまいります。
多くのグローバルブランドでは、グローバル本社が中心となり、大規模なビジネス戦略やプラン、およびグローバルキャンペーンの骨子を設計し、それを各市場に展開していると考えられます。
この体制は、ブランドビジネスが“ブランディング”の一貫性を保ちつつ、ブランドイメージを向上させつつ、ビジネスをドライブしていく必要があるという観点で、スピードや効率の面で非常に理にかなっています。
しかし、それが“そのまま”ローカル市場でも成功するとは限らない。
むしろ、ほぼ成功しない。
そのことを皆様も実感として感じているのではないでしょうか。
その理由は単純です。各国のお客様は、それぞれ異なる文化、生活文脈、購買動機を持っているからです。
例えば、私のキャリアの中でビューティーブランドを担当することが多くあったのですが、あるグローバルキャンペーンでは「美を叶えることで全てに前向きに、自信を持ち自立できること」を情緒的ベネフィットとして訴求することを想定しておりました。
ただ、皆様日本市場で生きる、いち“生活者/消費者”として少し考えてみてください。
どうでしょう、日本のお客様にとってどこまで感情移入可能でしょうか?
私は感情移入しづらい側面があるのではと感じました。
というのは、日本人ってそれほど自信満々で日々前向きに、というペルソナにそもそも親和性が薄いためです。(もちろん理想はそのような像だと思いますし、一律的に言えることではないと思っておりますが一般論としてご理解ください)
もっと、“肌荒れしているときに凹むから改善して1日の始まりを楽にしたい”“会社や友達と会うときに恥ずかしくない自分を演出したい”など、少しネガティブから入ったインサイトの方が親和性ありそうに感じませんか?
ただ一方で、グローバルブランドには“ローカルでは得られない強み”も確かにあります。
他市場の成功事例から得られる学びを素早く取り込む“再現性の高さ”、
そしてスケーラブルなメディア投資やコンテンツ展開によってROIを最大化できる土台があることです。
問題は、“どちらが正しいか”ではなく、両者をどう接続し、適応させていくかです。
3章: “編集” vs “翻訳”:消費者起点での再設計思考
多くのブランドマネージャーが直面する壁に、「グローバル本社の意図をどう解釈し、どうローカル市場に展開するか」があります。
しかし、私はこの考えをあえてこう言い換えたい。
“翻訳者”ではなく、“編集者”になれ
グローバル本社の意図を正しく理解することは重要です。しかし、それだけで終わってしまえば、消費者との接点で“伝わらないコミュニケーション”を量産する結果になりかねません。
編集者的思考とは、グローバル本社のフレームを一度ご自身の対峙している市場・お客様起点で咀嚼・分解し、再構成する力を指します。
実際、私もこれまでグローバル本社から届いたキャンペーン、コンテンツ・コミュニケーション提案を、そのまま実施することはほとんどありませんでした。
常に私が考えていたことは、「このキャンペーン・コミュニケーションは、今の日本のお客様のどんなインサイトやニーズに刺さるのか?」でした。
コミュニケーションの大きな方向性は変わらずとも、それをどのように“編集”して“伝達”するかでキャンペーンは豹変します。
編集の鍵は、「消費者起点」と「ブランディング」の両立です。
どちらかを犠牲にするのではなく、両立させる仮説を持ち、検証を重ねる。
これが、ブランドマネージャーに求められる思考です。
4章:「消費者起点マーケティング」の威力
これまでの複数社・複数ブランドでの経験を通して、私が何よりも学んだのは、「成功するマーケティングは、必ず消費者の解像度が高い」ということです。
たとえば、あるキャンペーン施策を実施する際に、当初グローバル本社的な意向としてはグローバルの素材を日本市場向けにそのまま活用する予定でした。
ビジュアルは洗練され、ストーリー性もある。
けれど、日本のターゲット層が抱えていた“肌の悩み”や“商品選定プロセス”とは、微妙にズレていたのです。
そこで私たちがまず立ち返ったのは、“日本のお客様が何に悩んでおり、これまで我々のブランドを使用したことが無い人のブランドイメージはどこにあり、何が理由でご使用いただくに至ってないのか?”―“お客様の声”です。
これを確認するにあたり、定常的に実施している定量調査の結果をつぶさに見ることに加え、急遽お客様へのデプスインタビューを設定しました。
インタビューの時も我々の戦略やプランに関して直接的に話を聞くのではなく、究極のインサイト発掘にフォーカスします。
すなわち、お客様はこれまでの人生の中でどのように美容商品・サービス遍歴を辿ってきて、どのようなブランド・商品を選んできたのか。その時にはどのような悩みがあったり、ライフステージの変化や心境・外部要因の変化があったのか。
そのような問いを繰り返すことで、ただのインタビュー対象者ではなく、“1人の生活者”のインサイトがそこに浮かび上がってきます。
その後は、当該インサイトに刺さるようなブランド側の武器は何があるのか―ブランドイメージ・アセット・グローバルキャンペーンの要素や商品特性等を鑑み、プラン検討・設計しました。
その結果、売上・新規顧客獲得数も大きくターゲットを上回る結果を導出することができました。
これらの成功の根底にあったのは、グローバル本社戦略を否定するのではなく、「市場の文脈に即した解釈と再設計」でした。
グローバル本社との対話でも、「なぜこの変更が必要なのか」を消費者データと仮説で丁寧に伝えることで、むしろ歓迎され、グローバル施策へのフィードバックにもつながりました。
消費者を深く理解し、その“解像度”でプランを組む。
それが、結果としてブランドの成長スピードを加速させる鍵になると、私は確信しています。
5章:“遠慮”が最大の機会損失:日本人マーケターが持つべき交渉力
日本市場のマーケターの多くは、グローバル本社に対して「No」と言うことに慎重な方も多いのではないかと推察します。
そもそも、提案に異を唱えたり、修正案を出したりすることに、“空気を読む”日本的な価値観が働いてしまうことは珍しくありません。
しかし、グローバルブランドにおけるローカルマーケターの最も重要な役割は、消費者の声をグローバル本社に確実に届けることと、自身の対峙する市場のお客様が求めているものを提供するという両者への“橋渡し役”です。
グローバル本社はすべてを知っているわけでもなければ、特定の市場だけにバイアスがかかっている、もしくは、そもそもプランの解像度が低い場合がほとんどです。
ビジネス戦略・プランニングベースでは特段大きな問題がなくとも、ひとたび実際お客様に問いかけるキャンペーンやクリエティブに話が移ると、そのままのローカル展開は機能しません。そして、そのままのローカル展開をグローバル本社も一切望んでいません。確実に言い切れます。
むしろ、ローカルのマーケターにしか見えないリアルな消費者インサイトや市場の潮流がある。
それを共有・それに基づいたローカルでのアクティベーションに落とし込むことこそが、ブランドの未来にとって最も価値ある貢献になるのです。
自身のキャリアにとっても、グローバル本社と対等にディスカッションし、提案をリードする姿勢は非常に重要です。
しかしそれ以上に、「お客様の幸福最大化」のために必要な変化を恐れず提言することが、真に意味のある行動だと私は信じています。
グローバル本社との対話は、“主張”ではなく“提案”であり、“敵対”ではなく“協創”です。
6章:明日から変われる、消費者起点戦略3ステップ
最後に、読者の皆さんが明日から実践できる「消費者起点で動く3つのステップ」をご紹介します。
Step 1|コンシューマージャーニーを“チームで”見える化する
消費者の購買行動は、デバイス・チャネル・心理で分断されています。
これをマーケティング・営業・Eコマース・PRなど部門横断で一枚の地図に描き、共通認識を持つことが、戦略の解像度を大きく上げます。
そして、そこへの疑念がフィールドで見えた、PR活動で見えてきたなどがあったときにすぐに議論の俎上に上げることができる、定期的なチームミーティングも必須だと思います。
Step 2|グローバル本社からの情報を“指示”と受け取らず“仮説ベースで問いを立てる”
グローバルの資料をそのまま実行するのではなく、「このメッセージは日本の消費者の感情に響くか?」「既存のコンテンツで本当に十分か?」と常に“お客様起点”で問いを立て、必要なら仮説・修正案を提示・議論したうえで、本当にお客様が求めるものを希求する姿勢を崩さないようにすることが肝要です。
Step 3|常に“お客様起点”での思考・行動を忘れないこと
ビジネスプラン・キャンペーン・クリエイティブを作成するとき、どのようなフェーズであってもまずは一度“これはローカル市場にいるお客様にとって役立つ・求められていることなのか”に立ち返ることが非常に重要です。我々はマーケターであり、ビジネスパーソンとして、時にブランドの“やるべきこと・やりたいこと”を第一に考えがちな傾向にあります。(私も勿論そうです)
だからこそ、常に立ち返る姿勢とクセをつけていくことが一つ大きな一歩ではないかと考えております。
「あなたの提案が最も消費者に届くと感じる」──そう言われるようになることが、真の影響力を持つローカルマーケターへの道です。
7章:「目の前の一人」に向き合うことが、ブランドの未来を動かす
グローバル戦略、グローバル本社との交渉、コンシューマージャーニー、あらゆる仕組みや手法の話をしてきました。
けれど最後に、私が最も大切にしている考え方をお伝えします。
それは、「すべては目の前の一人のお客様のためにある」ということです。
膨大な市場調査やデータも重要ですが、その先にいるのは、ひとりひとりの生活者。
商品を手に取るときの迷い、買うかどうかで悩む瞬間、試してみて良かったと感じる感情。
そうした“生の感情”にどれだけ真摯に向き合えるかが、ブランドの価値を本当の意味でつくると私は信じています。
もし、今日の記事でひとつだけ持ち帰っていただけるなら、こう伝えたいです。
「グローバル本社や上司ではなく、あなたの目の前にいる“お客様”こそが、ブランドのボスです。」
いかがだったでしょうか?
カイコクは、ブランディング/グローバルブランディングのプロ人材が多数登録しています。
プロ人材に依頼してみたい、詳しい話を聞きたいという方はこちらからお問い合わせください。

マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。