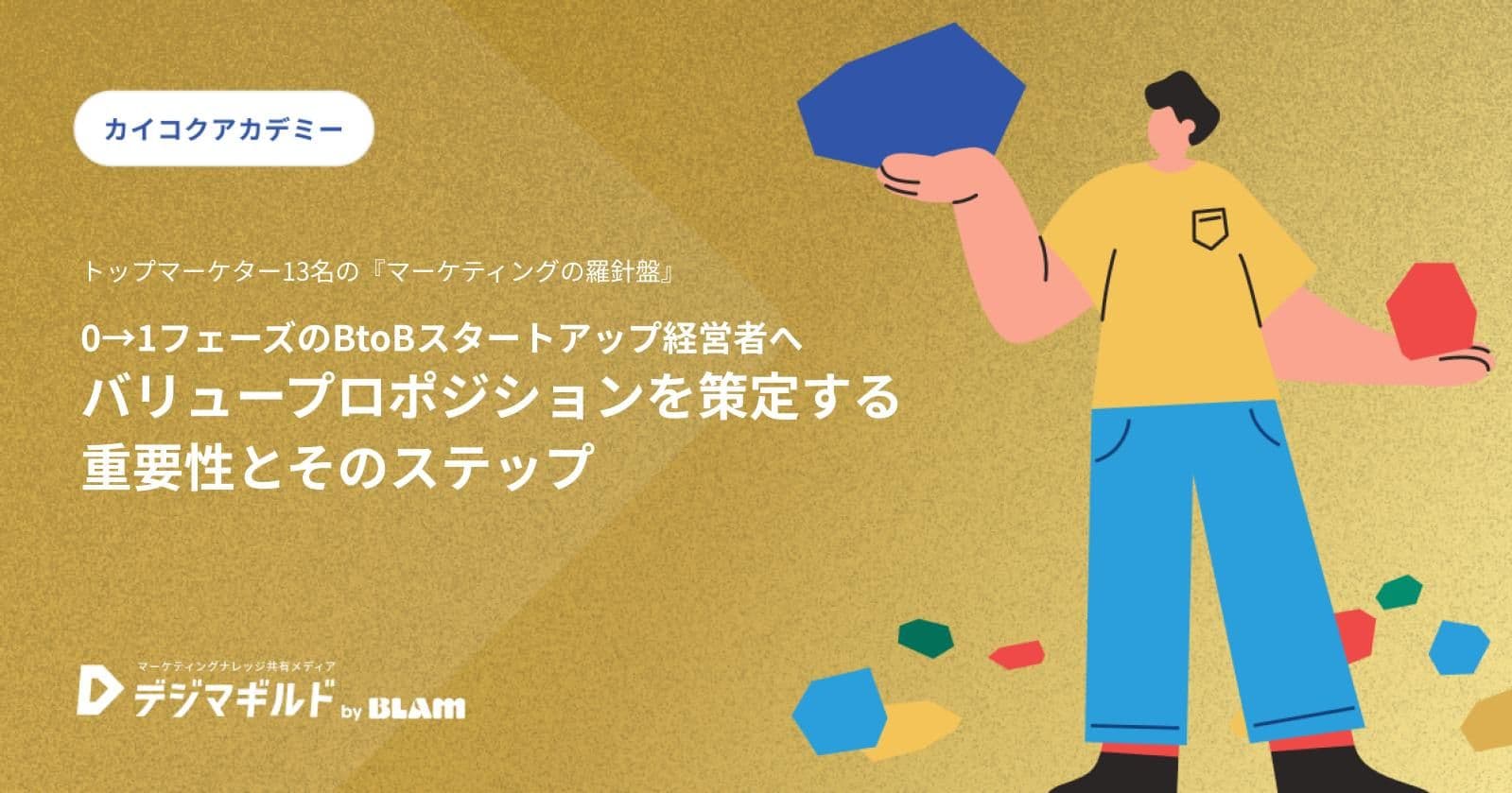カイコクアカデミー
リードを「真の顧客」に変えるCRM/MA戦略:HR系SaaS企業の現マネージャーが語る、ナーチャリングの本質

今日のビジネス環境において、企業の持続的な成長には、単にリードを獲得するだけでなく、それを「真の顧客」へと育成し、強固な関係を築く「ナーチャリング」が不可欠です。
特にBtoBマーケティングでは、このナーチャリングの質が企業の競争力を大きく左右します。
本記事では、HR系SaaS企業でナーチャリング領域のマネージャーを務める筆者が、いかにして中長期的な事業成長に繋げ、顧客との「血の通ったコミュニケーション」を実現するのか、その実践的な方法論をお伝えします。
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
ナーチャリングの本質:「ファン化」こそがゴールである
そもそも「ナーチャリング」とは何でしょうか。
一般的には「獲得したリードを商談や売上につなげる活動」と説明されます。リードに対してホワイトペーパーを提供したり、ウェビナーでサービスを詳しく説明したり、といった手法を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、ここには多くの企業が陥る大きな誤解があります。
それは、顧客は「貴社のサービス情報」を必ずしも欲しているわけではない、という事実です。
「自社に興味があるからリードになったはずだ。だからサービスの情報を提供しよう」。この考え方は自然ですが、顧客の真の目的はサービス購入そのものではなく、「自社の課題を解決すること」、あるいは「課題の本質を理解すること」にあります。
事実、私が支援した多くの企業で「自社サービスの紹介」と「課題に対する複数の解決策の紹介」という2つの内容でメルマガのABテストを行うと、ほとんどの場合で後者の反応率が上回りました。この顧客心理を見過ごしたままでは、せっかく獲得したリードが離れていってしまうことにもなりかねません。
そこで重要になるのが、ナーチャリングを単なる「売上創出の手法」ではなく、「顧客にファンになってもらうための一連のプロセス」と捉え直すことです。
「売上創出」が目的だと、施策は商談などの短期KPIに直結する「サービス紹介」に偏りがちです。しかし、「ファン化」をゴールに置けば、施策の質は大きく変わります。例えば、以下のような変化が生まれるでしょう。
- 一方的なサービス紹介をやめ、業界の最新ニュースや課題解決のヒントを提供する
- 情報を送りつけるだけでなく、アンケートなどで顧客が本当に知りたい情報を尋ねる
ナーチャリングとは、「顧客との対話を通じてファンになってもらうプロセスである」。まずは、このように定義をアップデートしてみてはいかがでしょうか。
が
プロをマッチング!
ナーチャリングの最適KPIは何か?
では、ナーチャリング活動における最適なKPIとは何でしょうか。
「商談数」や「受注額」を挙げる人もいれば、「メルマガの開封率・クリック率」を挙げる人もいるでしょう。
私が提案したいのは、「ナーチャリングを通じて、顧客が継続的にアクティブであるか」を測る指標です。具体的には、以下の3つをおすすめします。
① 配信停止率
この指標は、顧客があなたの会社からの情報を「価値あるもの」と判断しているかを示すバロメーターです。提供する情報が顧客の求めるものから乖離すれば、配信停止率は上昇します。これは、獲得したリードという貴重な資産を失っている危険なサインです。「ファン化」という目的において、配信停止率を低く抑えるコミュニケーション設計は極めて重要です。
② 継続反応率
個々の施策の反応数に一喜一憂するのではなく、特定の期間における顧客一人の反応の「継続性」に着目します。ある施策に反応しなかった理由は、「興味がなかった」のかもしれませんし、あるいは単純に「多忙で気づかなかった」だけかもしれません。
継続反応率は、そのどちらの理由であっても顧客とのエンゲージメントの深さを測る上で有効です。例えば、3ヶ月で10回の施策を実施した際、「1回だけ反応した顧客」と「7回反応した顧客」では、後者の方があなたの会社からの情報を有益だと感じている可能性が高く、ファン化の一歩手前にいると判断できます。
③ 自社サイトのウェブ回遊率
メルマガなどの施策に反応しても、その後の行動に繋がらないケースは少なくありません。そこで、施策接触後の「自社サイト内での回遊率」を計測します。
サイト内を回遊しているという行動は、顧客が貴社サイトを能動的に活用し、課題解決のヒントを探している証拠です。期間を区切ってこの回遊率をKPIに設定することで、施策が本当の意味で顧客の興味を喚起できているかを測ることができます。
私が過去支援させていただいた研修の企画・販売を手掛ける企業様は、上記②と③の指標を主において施策に取り組んでくださいました。②の継続反応率をもとに、顧客をセグメントしメルマガの配信内容・頻度を変えることで、クリック率が120%以上改善しました。また③の指標を意識することで、直接商談などに繋がっていないがウェブ回遊というアクティビティにつながっていたという事実が見つかり、ウェブ上でのコンテンツをブラッシュアップすることでウェブ経由の商談獲得増に貢献した事例があります。
これらの指標をKPIに据えることで、結果として商談や売上につながるだけでなく、たとえ短期的な成果が出なくとも、中長期的な事業貢献への確かな手応えを感じられるはずです。
成果を急ぐ企業が陥る「ABテストのジレンマ」
最後に、ナーチャリング活動で多くの企業が陥りがちな「ABテストのジレンマ」についてご紹介します。これは私の造語ですが、「成果を出すためにABテストを行い、勝ちパターンの施策を実装したにもかかわらず、なぜかテスト前と成果が変わらない」という現象を指します。
ABテストで優位な結果が出たのだから、実装すれば全体の反応率は向上するはず。そう期待するでしょう。しかし、現実はテスト前と横ばい、ということも少なくありません。「結局、ABテストに意味はあったのか…」と不安になるかもしれません。
しかし、ここでお伝えしたいのは、ABテストを続ける「プロセスそのもの」に絶大な価値があるということです。
もしABテストをしなければ、顧客はいつも同じような、画一的な情報ばかりを受け取ることになります。同じコミュニケーションを繰り返す相手のファンになるのが難しいことは、容易に想像がつくでしょう。
例えば、私が支援していたある企業では、ABテストで勝ったクリエイティブを本番実装したのですが、ABテストの結果とは異なり反応率が下がってしまったクリエイティブがありました。そこで、ABテスト実施前のクリエイティブに戻したのですが、なんとABテスト実施前よりもかなり低い結果にしかならなかったという経験があります。つまり、ABテストで反応率が下がったクリエイティブであっても、ずっと同じクリエイティブを使い続けるよりは、結果として良い成果を出せていた、ということです。
勝ちパターンの実装後、全体の反応率が期待通りに伸びなかったとしても、「顧客とのコミュニケーションを変化させ続けることができた」という事実が重要だということを実感した瞬間でした。ABテストは、顧客を飽きさせず、常に関心を引きつけるための重要な対話活動だと捉えましょう。
経験豊富なマーケターがすぐ見つかる
おわりに
ナーチャリングとは、顧客一人ひとりを「数値」ではなく「人」として捉え、中長期的な視点で関係性を構築する営みです。
そこに「これをやれば必ず成功する」という方程式は存在しません。常に顧客が何を求め、何を根本的に欲しているのかを考え、試し、そしてまた考える。その試行錯誤のプロセスの中にしか、自社オリジナルの成功パターンは見つからないのです。
本記事が、皆様のナーチャリング活動をアップデートする一助となれば幸いです。
が
課題解決をサポート!
いかがだったでしょうか?
カイコクは、原さんのようにCRM/MA領域のプロ人材が多数登録しています。
原さんのようなプロ人材に依頼してみたい、詳しい話を聞きたいという方はこちらからお問い合わせください。

マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人
原 聡汰
HR系SaaS企業のナーチャリング部でマネージャー。副業という形で複数社のナーチャリング戦略の企画を担当。 ex.株式会社カーブスジャパン、パーソルキャリア株式会社(旧株式会社インテリジェンス)