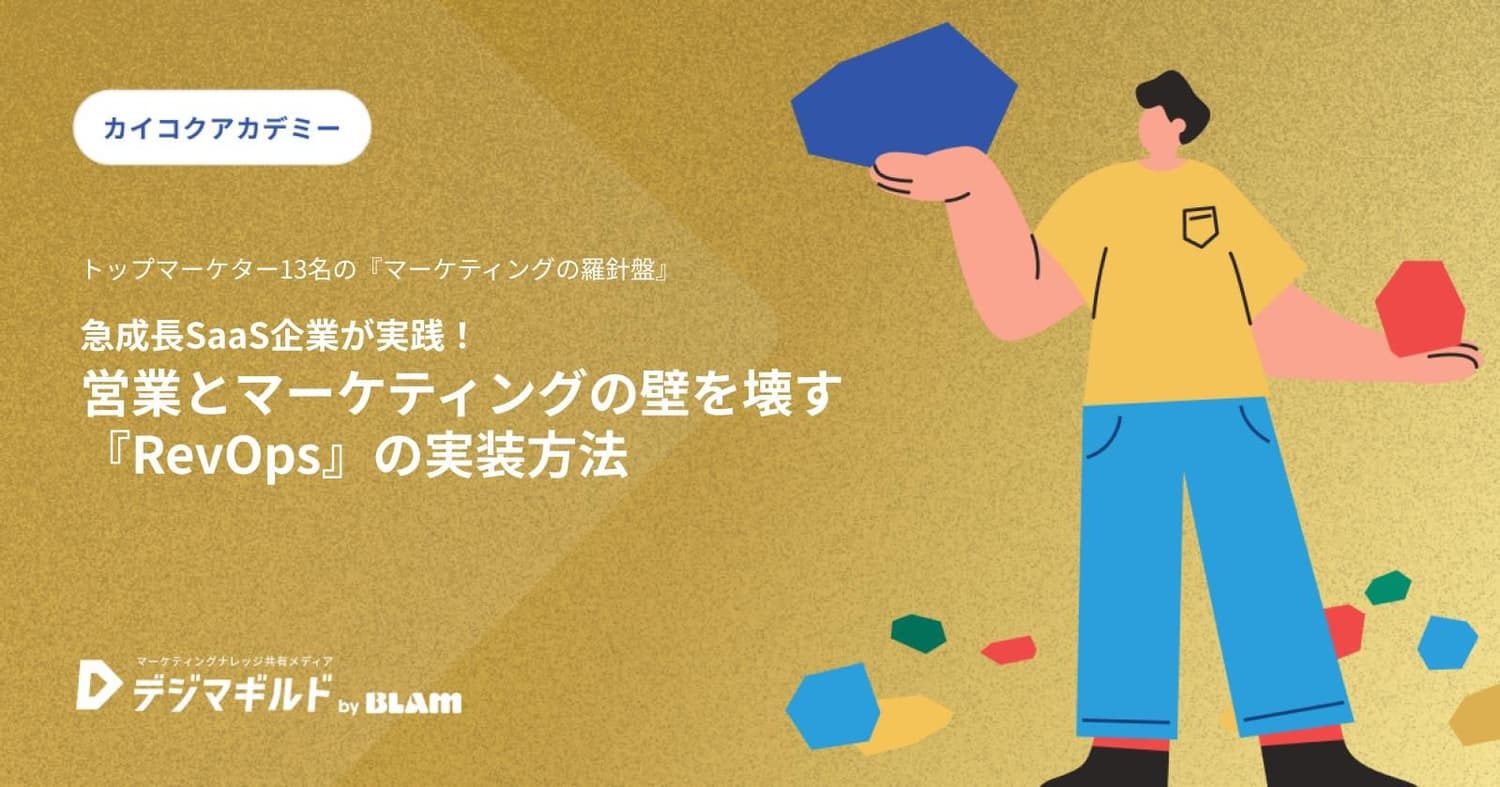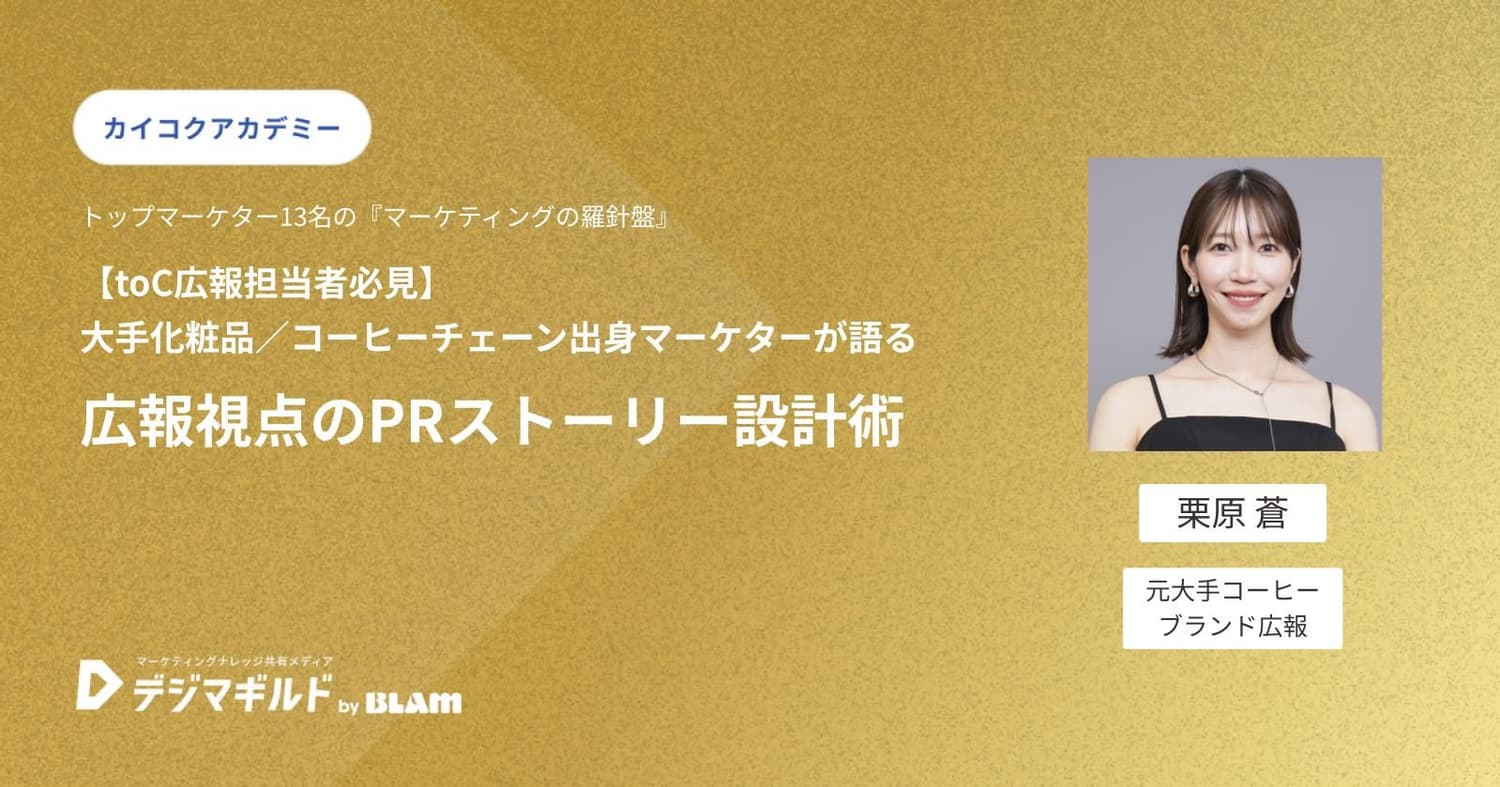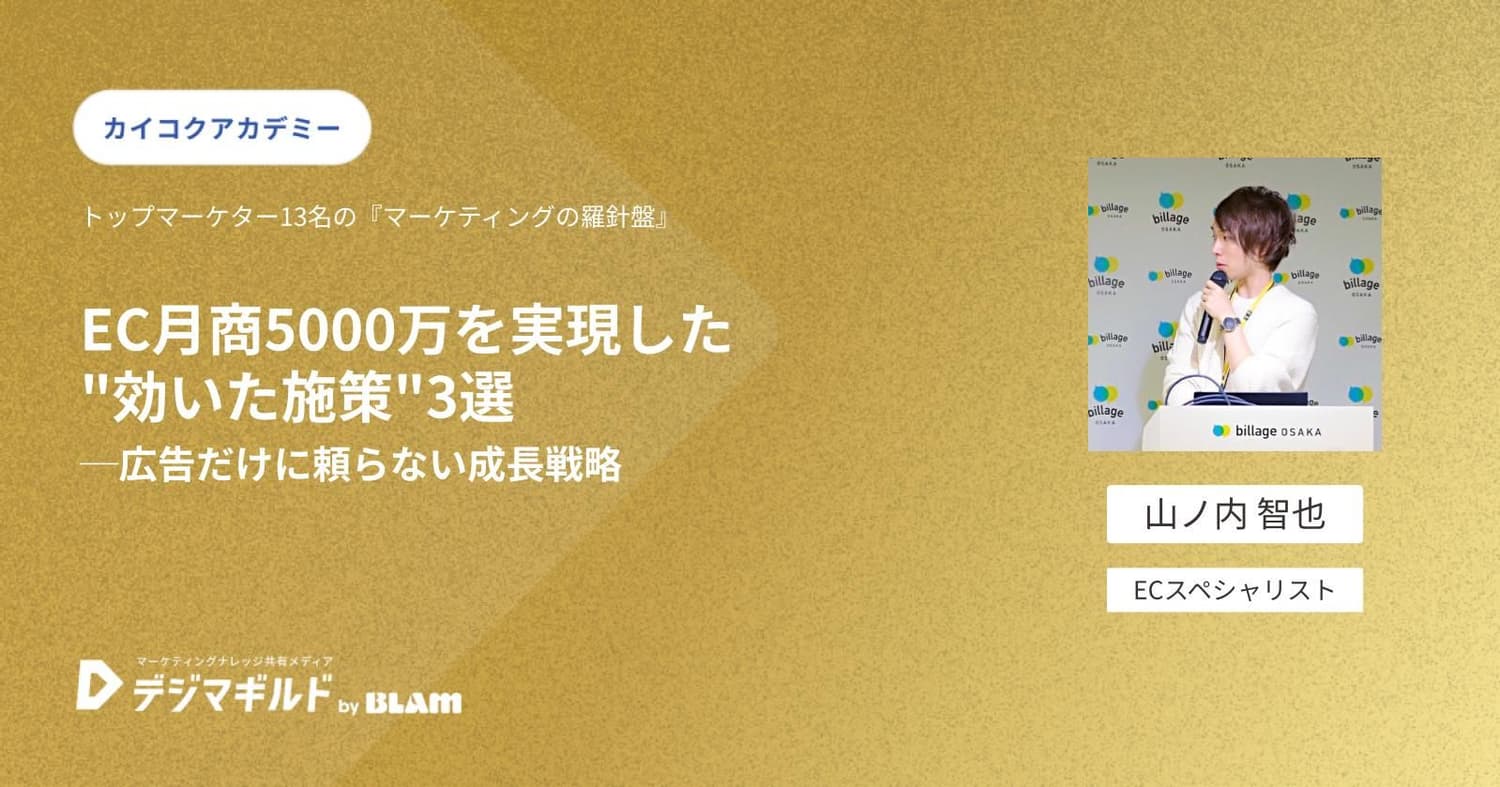カイコクアカデミー
支援歴30社以上!フリーランスとして活躍する元SATORIマネージャーが語る:顧客体験設計とデータドリブンなリードナーチャリングの全貌
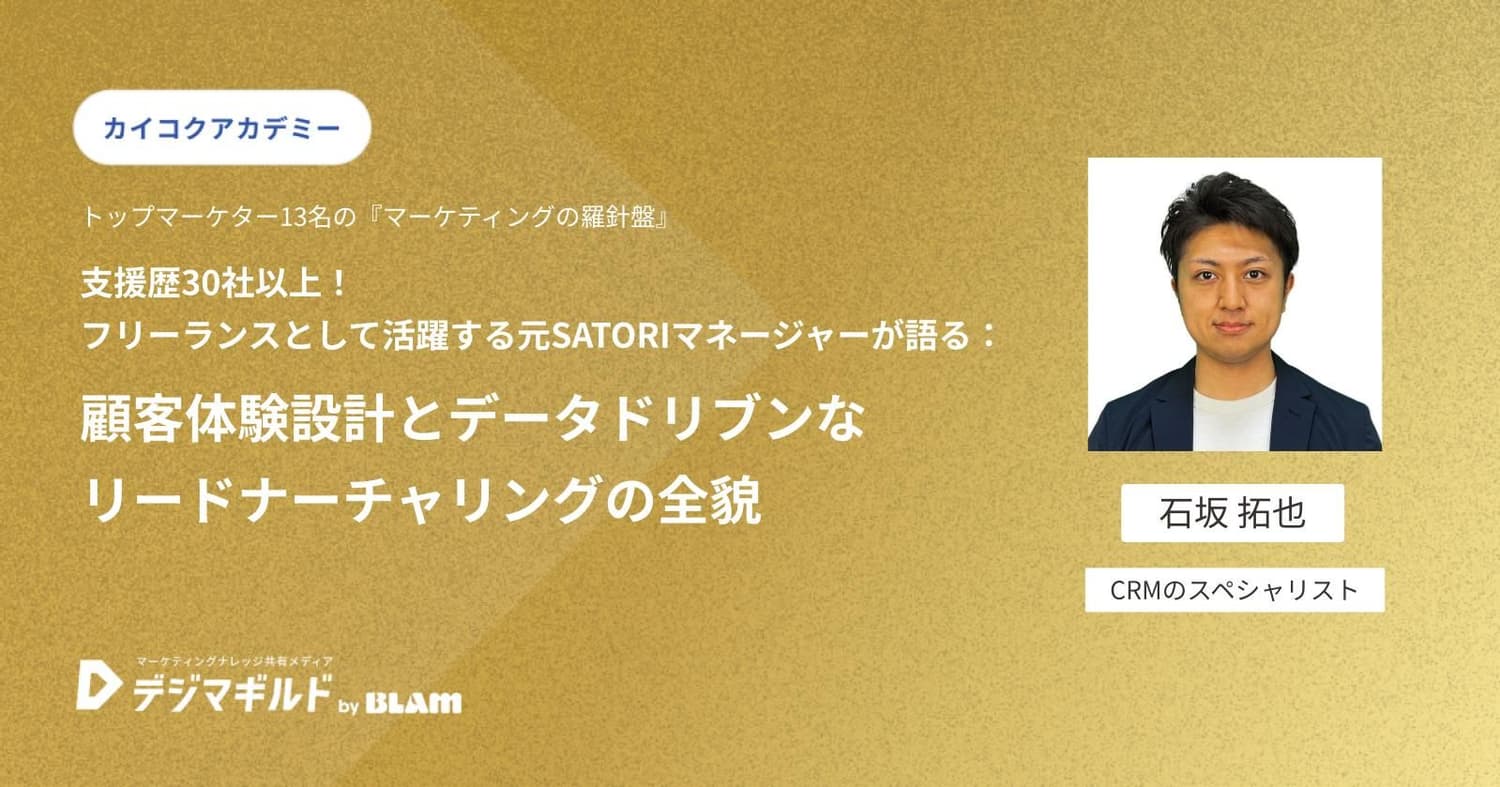
1. はじめに
BtoBマーケティングの現場で「成果が出ない」と感じている担当者は少なくありません。私自身、30社以上の企業を支援してきたなかで、同じ課題に直面して悩む多くの現場を見てきました。「なぜ、頑張っているのにリードが増えないのか」「施策を積み重ねても、商談につながらないのか」――その背景には、表面的なノウハウやツール導入だけでは解決できない課題が潜んでいます。
特に、カスタマージャーニーの設計と、そこと紐づけた施策のファネル設計を“仕組み化”できていない企業が多いことを実感しています。このことと繋がっていますが、CRMやMAを導入しても、運用が属人化してしまい、全体最適ができず部分最適に留まっているケースも散見されます。
本記事では、単なる理論ではなく、私自身が現場で実践し、実際に成果をあげた「データドリブンなリードナーチャリング」と「顧客体験設計」のノウハウをできるだけ体系的にお伝えできるよう、まとめました。
読者の皆さまには、「成果が出ない」現状から一歩抜け出すためのヒントや、明日からすぐに実践できる具体策を持ち帰っていただければ幸いです
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
2. 事例取材とカスタマージャーニー設計
2-1. 事例取材の重要性と実践ポイント
まず、“成果が出ない”現場の多くで共通する課題が、「自社の顧客像を具体的に捉えきれていない」という点です。どんなにMAやCRMなどのデジタルツールを駆使しても、根本となるペルソナ像や実際の顧客の購買プロセスが曖昧なままでは、マーケティング施策は空回りしてしまいます。
そこで初めの一歩としてぜひ実践すべきことが「事例取材」です。
事例取材が重要な理由は二つあります。
一つは、“強力な商談創出コンテンツ”として活用できること。実際のお客様の成功ストーリーや導入理由、効果を可視化することで、他の見込み顧客にとっても説得力のある営業材料となります。
もう一つは、「理想的な顧客の行動・情報収集手段を明らかにできること」です。
受注までのリードタイムが短かった理想的な顧客をリストアップし、直接ヒアリングすることで、購買行動の実態や各フェーズで活用したチャネル・意思決定プロセスを具体的に把握することができます。
この情報が、後のペルソナ設計やカスタマージャーニー設計の核となり、より精度の高いマーケティング戦略の土台となるのです。
取材時には、以下のような質問を投げかけることをお勧めします。
- 「御社が当社のサービスを知ったきっかけは何でしたか?」
- 「実際に情報収集を始めたのは、どのような課題意識からでしたか?」
- 「比較検討時、他社と迷ったポイントは?」
- 「決め手になった要素や、導入後の変化は何でしたか?」
- 「情報収集は普段どのようなチャネルを活用していますか?」
このようなヒアリングを通して、“顧客の購買行動プロセス”と“企業と顧客の接点”を洗い出します。
また、ヒアリング内容は営業・マーケティングだけでなく、開発やサポート、バックオフィスなど様々な部署への波及効果も意識して確認すると、より解像度の高いペルソナ像を描くことができます。
2-2. ペルソナ定義のコツ
BtoBマーケティングにおいては、決裁者だけでなく現場担当者、DX推進担当、購買部門、時には経営層まで、複数のステークホルダーが購買意思決定に関与します。
そのため、単一のペルソナではなく、「部署ごと・役割ごと」にペルソナを設計し、それぞれのニーズや課題、情報収集チャネルを細かく分解しておくことが不可欠です。
例えば製造業であれば、DX推進室・工場長・購買部門・生産企画など、実際の案件で関与した部署ごとに“理想的な受注ケース”からヒアリングを重ね、要素を整理します。
ペルソナごとにカスタマージャーニーを設計することで、「認知」「興味」「比較検討」各フェーズで打つべきメッセージやコンテンツの最適化が可能になります。
2-3. カスタマージャーニー設計のプロセス
カスタマージャーニー設計の大前提は、「顧客の購買行動・心理変容」を具体的なストーリーとして落とし込むことです。
私が実際の支援現場で重視しているプロセスは下記の通りです。
- 認知フェーズ
潜在課題を“言語化”し、顕在課題として認識させる。
例:「DX推進の必要性は感じているが、具体的なアプローチがわからない」→「そもそも製造業のDXの手立てとしては、調達や勤怠、現場管理に関するものがあり、特に調達のDXが遅れていることは経営リスクである」と伝える - 興味フェーズ
顕在課題の“深刻度”や“放置した場合のリスク”、解決後の“メリット”を伝えて、顕在課題の重要性を膨らませる。
例:「調達業務が非効率なままだと事務コスト・現場負担が増える/効率化すると現場の生産性が向上する」など - 比較検討フェーズ
顕在課題の解決手段の選択肢の1つとして自社サービスの検討材料を提供する。「自社サービスを導入した場合、どんな未来が待っているか」を具体的な導入事例やプロセス、実際の導入効果として伝えます。
これら各フェーズの“課題”や“メッセージ”を、事例取材で得たリアルな声を元に作り込むことで、机上の空論ではない「現場に刺さるジャーニー」が完成します。
3. ファネルごとの施策の仕組み化
BtoBマーケティングで成果を生み出すためには、カスタマージャーニーごとに施策を“仕組み化”し、再現性の高いオペレーションを確立することが重要です。現場の感覚や属人的なアプローチに頼るのではなく、「認知」「興味」「比較検討」といった各ファネル(階層)ごとに、どの施策がどの役割を果たすのかを整理し、組織全体で共有できる仕組みをつくる必要があります。
経験豊富なマーケターがすぐ見つかる
3-1. 認知フェーズ:市場全体へのリーチと“潜在層”の掘り起こし
認知フェーズでは、まだ課題が顕在化していない“潜在層”に向けて情報発信を行い、課題意識の醸成を目指します。
この段階で大切なのは、「誰に」「どんな課題を気づかせるべきか」というメッセージ設計と、「どのタッチポイント(接点)を使えば届くのか」という発信手段の選定です。
事例取材を通じて実際の顧客がどのチャネルで情報収集していたか、どの時点で自社サービスを知ったかなどの“接点”を把握しておくことで、
- 業界特化型のウェビナー
- 業界メディアでの寄稿
- 展示会・カンファレンス出展
- 専門誌広告や業界団体との協業
など、ペルソナごとに有効な発信手段を、より解像度高く選定できます。
たとえば、製造業向けのDXツールであれば、「2025年最新のDX事例【製造業版】」のような網羅的なセミナーを共催で企画し、現場担当者がよく閲覧している業界メディアにも記事を寄稿するといった“組み合わせ”で接点を増やします。
3-2. 興味フェーズ:課題の具体化と「行動喚起」
興味フェーズでは、認知段階で得た見込客に対し、「あなたの課題はここにあります」と言語化した上で、課題解決の必要性や課題を放置した場合のリスク、業務インパクトをしっかりと提示します。
たとえば――
- 「調達業務の非効率性により、余剰在庫や発注ミスが発生しやすく、管理コスト・現場負担が増大していませんか?」
- 「調達業務を効率化すると、現場スタッフが本来業務に専念でき、納期遅延やムダな業務ロスが大幅に減ります」
- 「効率化が進むと、工場全体の生産性や従業員エンゲージメントが上がり、採用・定着面にも良い影響が出ます」
- 「非効率なまま放置すると、調達コストが増大し利益率が下がるだけでなく、ヒューマンエラーやトラブルの温床になります」
といった形で、実際に現場で起きている/起きうる「問題」や「恩恵」を具体的に伝えることがポイントです。
この段階で有効な施策例
- 顧客インタビューに基づいた課題解決セミナー
(例:「発注ミスが減る!調達DXの実践術」など) - 専門分野に特化したホワイトペーパー
(例:「調達業務の属人化が引き起こす経営リスクと解決法」など)
ここでも重要なのは「次の行動」を明示することです。たとえば、
- セミナー後アンケートで「デモ体験」に誘導
- ホワイトペーパーの最後に「無料相談会」への申込導線を設ける
など、"課題を自分ごと化させた上で次のアクションを後押しする仕組み"を必ず組み込みます。
このように、ただ「業務を効率化しましょう」と言うだけでなく、「効率化することで得られる成果」「放置した場合のリスク」まで、数字や実態を交えて伝えることが、興味フェーズの施策で最も大事なポイントとなります。
3-3. 比較検討フェーズ:意思決定の後押し
比較検討フェーズでは、すでに課題が顕在化し、複数の選択肢を検討している見込客に対し、「自社の強み」や「価格・導入フロー」を論理的に訴求していきます。
この段階では、下記のような施策が有効です。
- 実際の導入事例を活用したウェビナーやカンファレンス
- 顧客の声・デモ動画・FAQコンテンツの充実
- 導入フローやサポート体制の可視化
現場でありがちな失敗は、見込客が比較検討フェーズに入ったタイミングで、いきなり「一度お打ち合わせしませんか?」とアプローチしてしまうことです。すると、納得感や安心感が不十分なまま提案段階へ進むことになり、結果として商談率が伸び悩みます。
カスタマージャーニーに沿って、比較検討フェーズまできた見込客には、迷いを払拭できる十分な情報と、「似たような企業でうまくいった」という“納得感”を提供することが重要です。
例えば、具体的な導入事例や比較表、他社との違いを明示したFAQ、実際の導入企業の声をタイミングよく届けることで、「自分たちにもできそう」「他社でも成功しているなら大丈夫だ」と一歩踏み出す心理的ハードルを下げることができます。この“納得感”を積み重ねた上で、「よろしければ個別相談に進みませんか?」とアプローチすることで、自然な流れで商談化へとつなげることができます。
一例として、ある人材系SaaSサービスのマーケティング支援を行った際には、特に数値成果が優れており、知名度の高いお客様の導入事例をもとに、顧客登壇セミナーを企画しました。リード獲得を目的とした共催セミナーの後に、この顧客登壇セミナーへ参加者を誘導することで、トレンドワードを知りたい層から自社サービスの具体的な訴求へと繋げることができました。
この顧客はゼロベースからサービスを導入し、成功を収めたケースだったため、多くの見込み顧客に親近感を持ってもらうことができ、関心度の向上と商談への転換に成功しました。
本セミナーはアーカイブ化し、3ヶ月に一度配信していますが、毎回安定して申し込みと商談を創出できています。
4. データドリブンな運用と効果測定
BtoBマーケティングにおいて“データドリブン”を標榜する企業は多いものの、実態としては「単に数字を眺めて終わり」「KPIを決めたはいいが、運用の現場に落ちていない」というケースが多く見受けられます。本当に成果を出すためには、全ての施策を“ファネルの移行”という視点で評価し、改善サイクルを組み込んでいくことが不可欠です。
4-1. ファネル移行率の可視化
まず重要なのは、各ファネル間での“移行率”を必ず可視化することです。
例えば、認知フェーズの共催セミナーに100名参加した場合、
- 興味フェーズの個別相談セミナーにどれだけ申し込んだか
- 比較検討フェーズの個別提案・デモへの進捗は何件あったか
という具合に、次のフェーズにどれだけ進んだかを計測します。
「リード数」「商談数」「受注数」など一般的な指標も当然追いますが、特に認知や興味フェーズの施策を“商談化率”だけで評価しないことがポイントです。
認知施策は商談化率が低くて当然。むしろ重要なのは、次のアクション(例えばダウンロード、個別相談申込など)につながった率なのです。
4-2. 施策ごとの改善アプローチ
移行率を見ながら、各施策のボトルネックや成果ポイントを発見し、仮説検証を繰り返すことで施策をブラッシュアップしていきます。
たとえば、共催セミナーから次のフェーズへの移行が鈍い場合は、
- セミナー後のフォローが不十分で、参加者のアクションを促せていない
- セミナー内容がファネルに応じて設計されていない
などの仮説を立て、アンケート設問を見直したり、終了後のフォロー施策を強化したりといった打ち手を実行します。
比較検討フェーズの施策に関しては「アポ率」「受注率」を厳密に管理します。MAやCRMでのトラッキングを徹底し、個々のリードがどの施策を経由し、どのタイミングで意思決定したのかまで掘り下げます。
4-3. “アポ率”と“移行率”──成果の捉え方と改善プロセス
比較検討フェーズ以外の施策(認知・興味フェーズ等)においては、アポ率(商談化率)そのものが低くても、ファネル内での“移行率”が十分に高ければ施策としては合格点と考えるべきです。
移行率とは、「認知→興味」「興味→比較検討」など、顧客がファネルの上流から下流へどれだけスムーズに進んでいるかを示す指標です。
施策を評価する際、移行率も低い場合には、企画そのものが想定したペルソナやカスタマージャーニーにきちんと沿っていない可能性が高くなります。
この場合は単に表現やチャネルを変更するだけでなく、以下の3つの要素をそれぞれ分解し、どの部分にズレや課題があったのかABテスト等で検証・再設計していくことが重要です。
- 想定したペルソナのリテラシー(前提となる知識や課題感)
- そのペルソナに刺さるメッセージ
- 適切な情報接点(チャネル・タッチポイント)
さらに、事例取材やインタビューの数を積み重ねることで、仮説の精度や答え合わせのサンプル数が増え、成果の再現性が高まります。
5. 明日から実践できるアクションプラン
ここまでお伝えした「事例取材」「カスタマージャーニー設計」「ファネルごとの施策運用」「データドリブンな評価・改善」を、実際にどう進めればよいのか。明日から現場で動き出せるアクションプランを整理します。
- 事例取材を必ず企画・実施:「なぜ商材を知ったか」「課題は何だったか」など最低限の質問項目で理想顧客を掘り下げる
- ペルソナ・カスタマージャーニー設計:受注案件から複数ペルソナを設定し、「どのチャネル・どの情報が刺さったか」を洗い出す
- ファネルごとの施策とKPI明確化:各フェーズで有効施策を整理し、「認知→興味→比較検討」の移行率を必ず追う
この仕組みが組織に根付くことで、リード獲得もナーチャリングも、「やりっぱなし」ではなく、日々のデータを活用しながら一歩ずつ強化できるBtoBマーケティング体制を築いていくことができます。
外注か採用か迷ったら
へ相談!
いかがだったでしょうか?
カイコクは、石坂さんのようにBtoBのリード創出やナーチャリングなど戦略設計に長けたプロ人材が多数登録しています。
石坂さんのようなプロ人材に依頼してみたい、詳しい話を聞きたいという方はこちらからお問い合わせください。
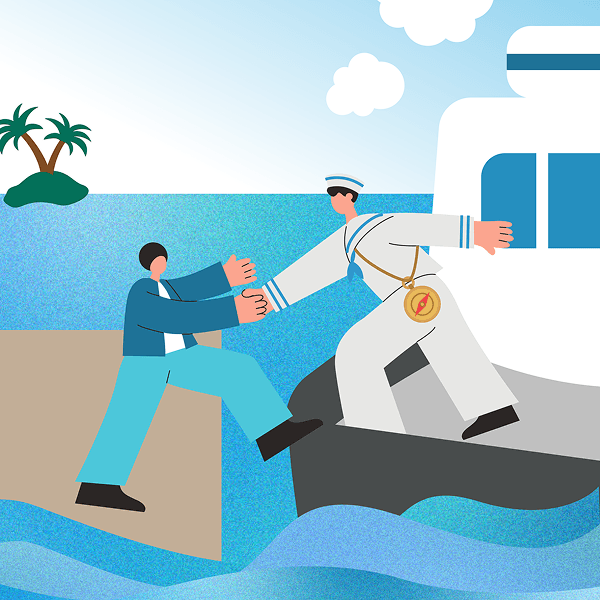
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人
石坂 拓也
CRMのスペシャリスト
Webマーケティング会社・大手Web広告代理店・スタートアップSaas企業などを経験し、マーケティング責任者や事業責任者として活躍。 その後、フリーランスのマーケターとして独立。現在は、主にBtoBマーケティングの戦略設計から実行支援までを行う。