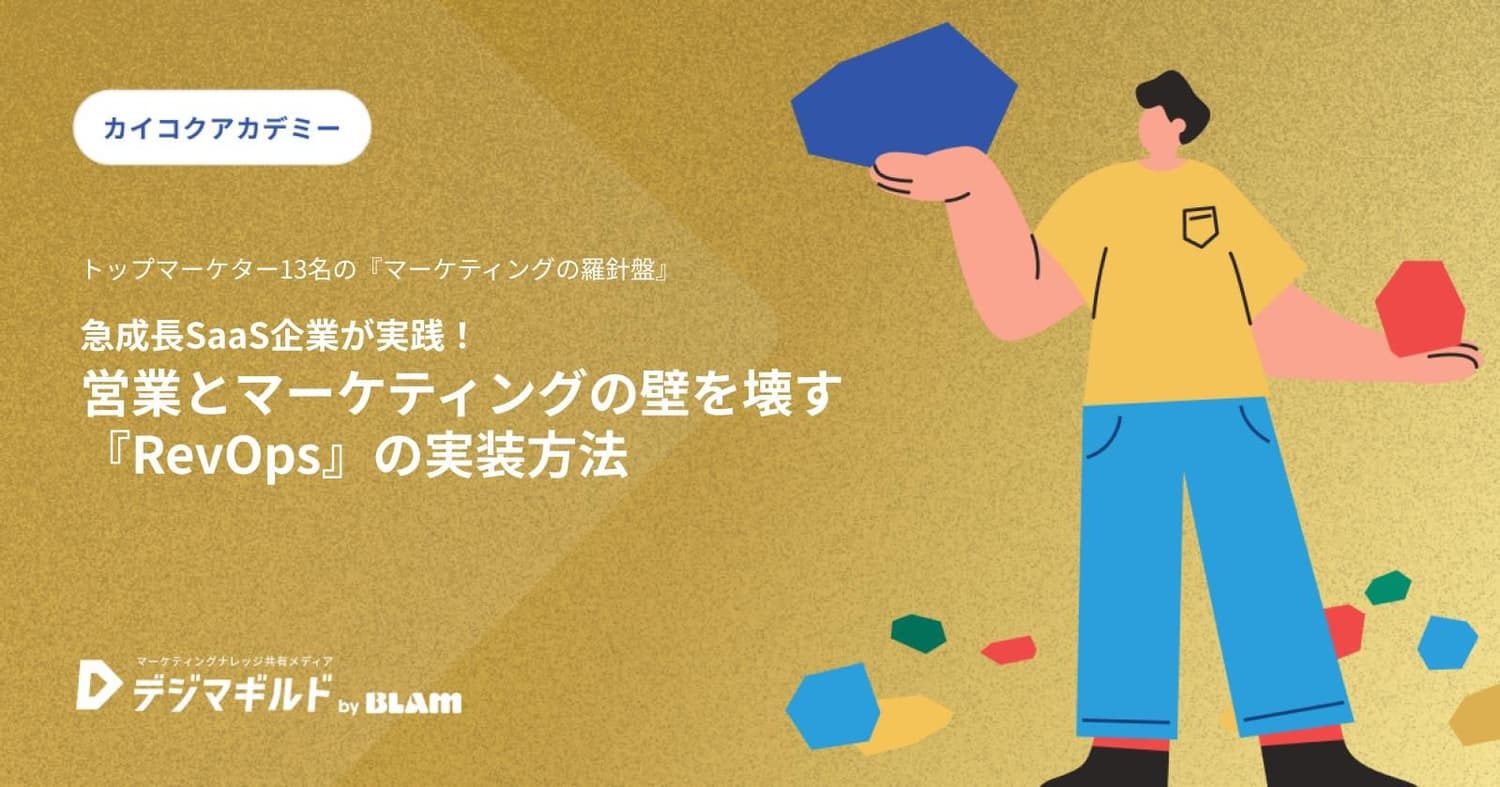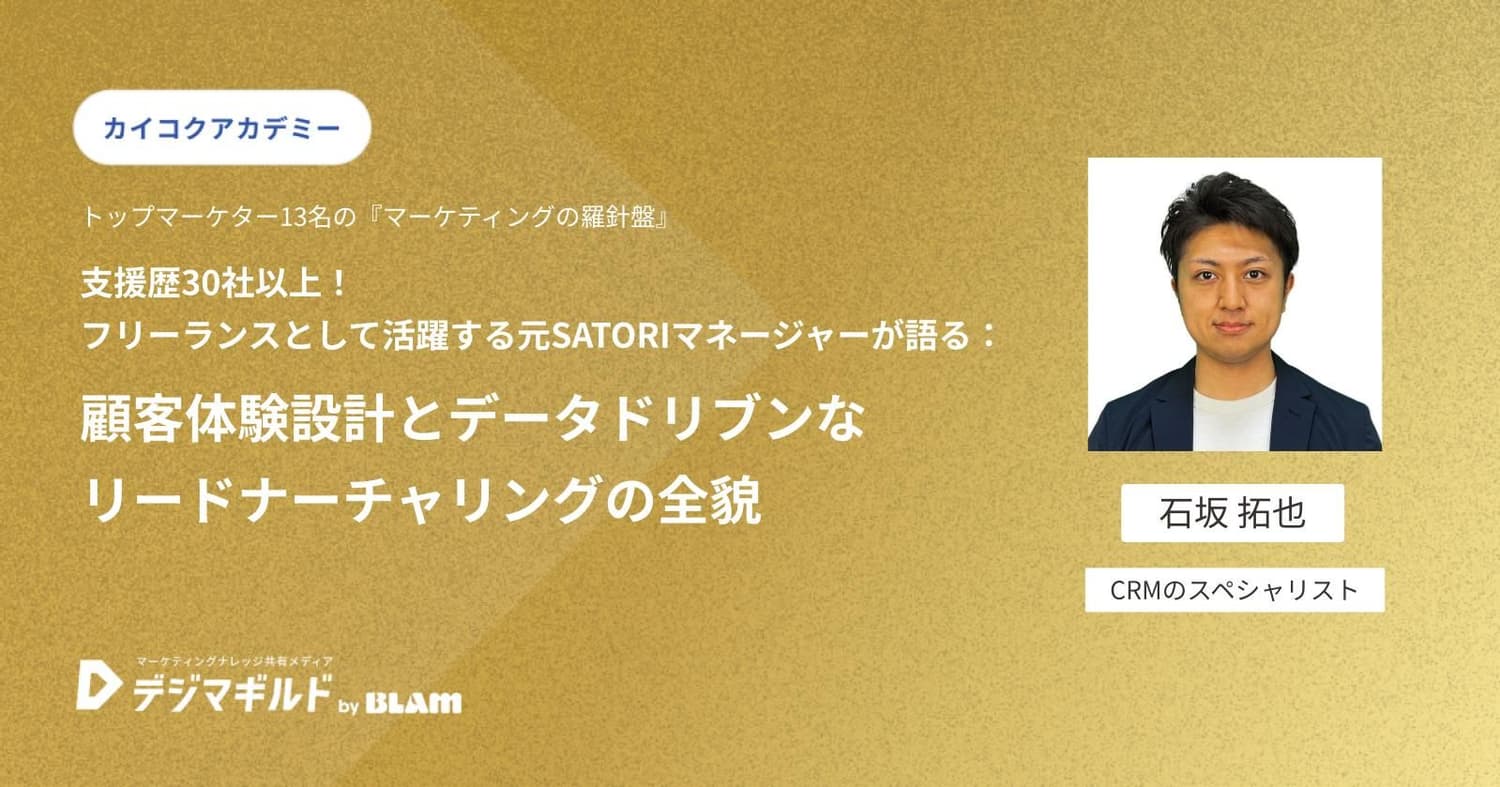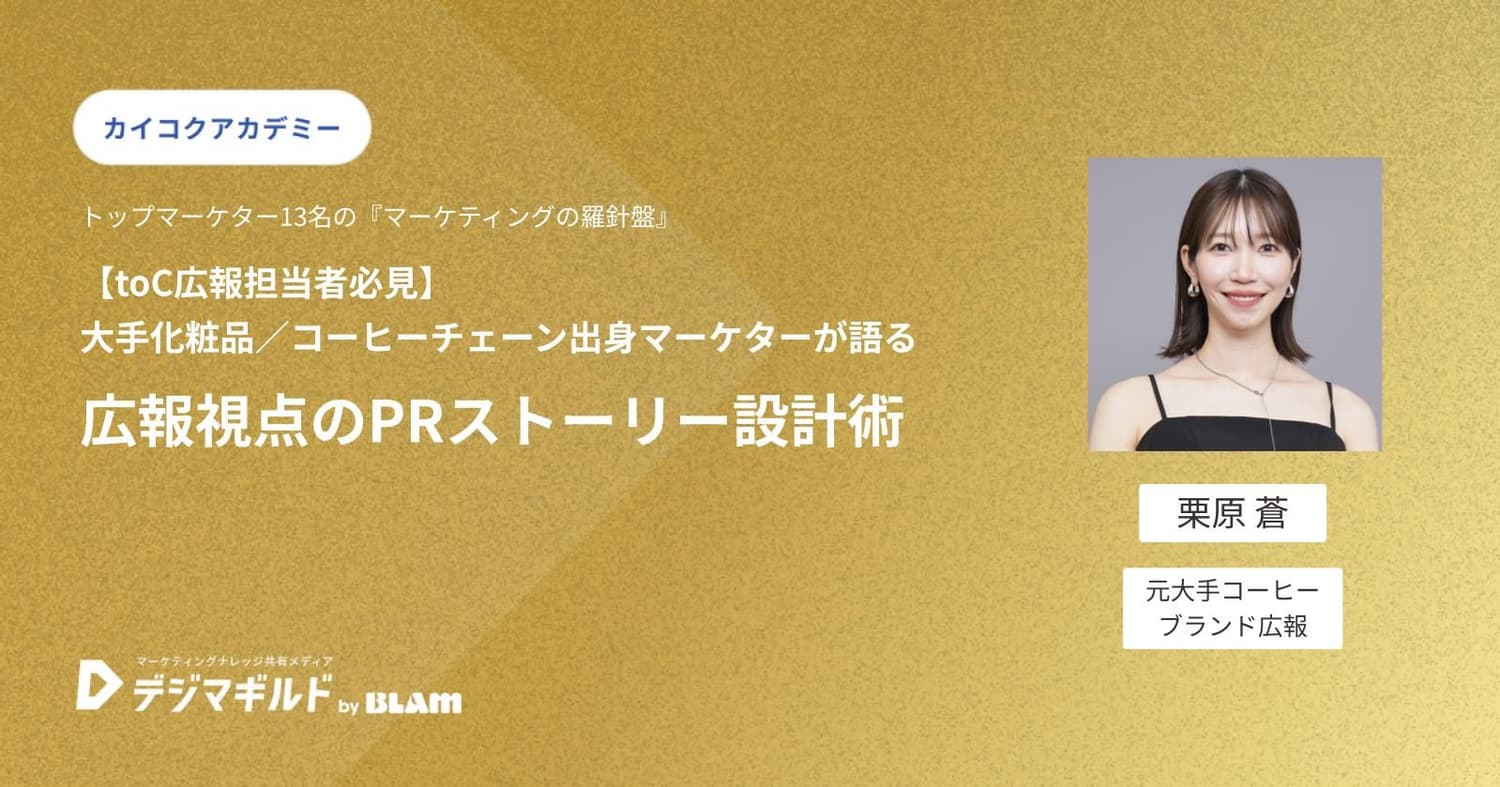カイコクアカデミー
企業が「生き抜く力」を生み出す、マーケティング組織の創り方 ~広告・コンサル・事業会社、3つの視点を通じて得た「企業のマーケティング力向上 」の要諦
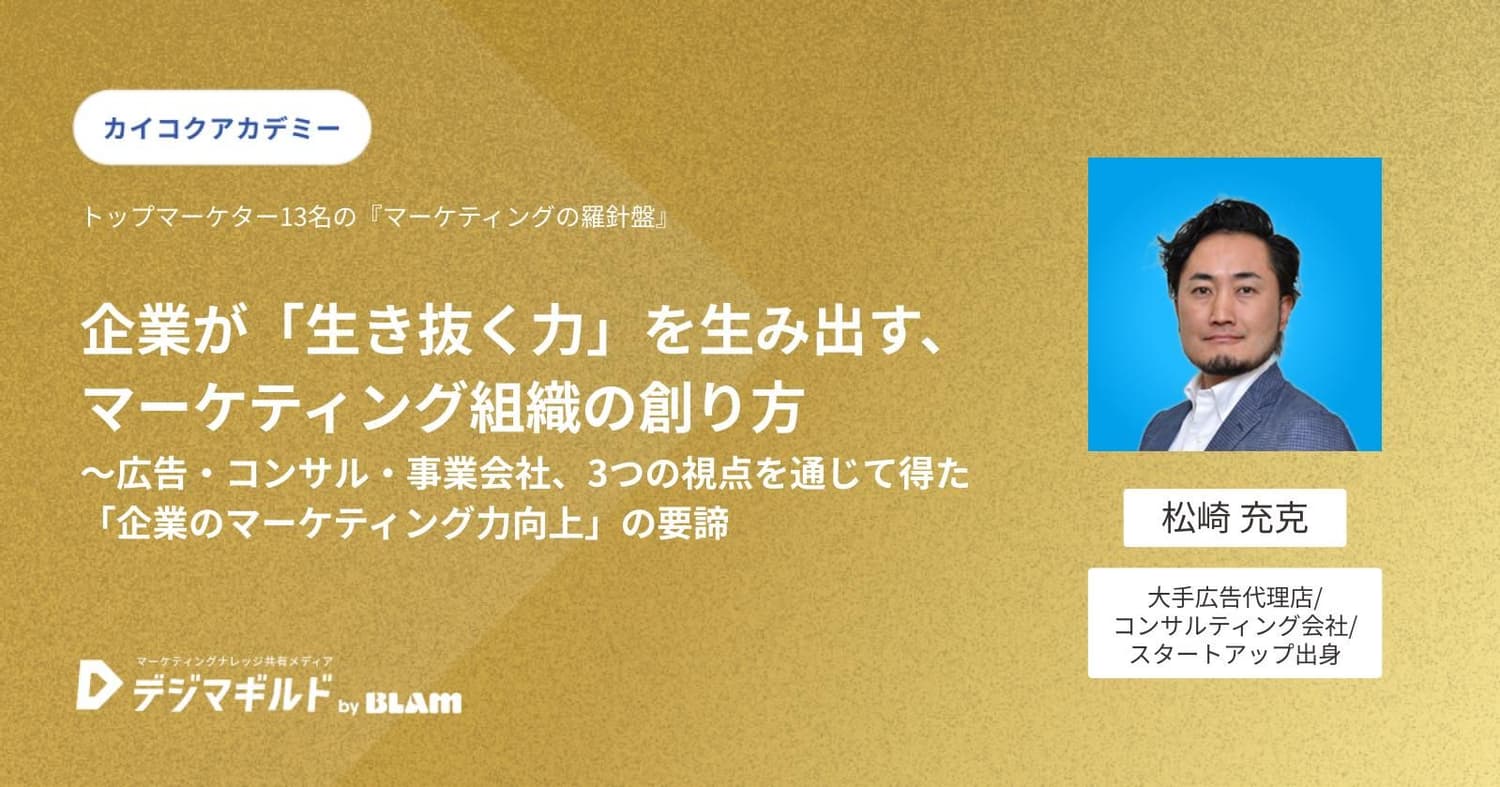
企業が成長していく道のりには、常に“変化”がつきまといます。
顧客ニーズは移り変わり、技術やチャネルは次々と更新され、競争環境も一様ではありません。
こうした変化の波にどう向き合い、どう自社を進化させていくのか。
その対応力が、いま多くの企業に「生き抜く力」として求められています。
今日、企業が「生き抜く力」を生み出す源泉として提案したいのが「強いマーケティング組織を創ること」です。
マーケティングは、単なる「売るための仕組みづくり」ではありません。市場や顧客を見つめ、変化の兆しを捉え、問いを立て、次の打ち手をつくり、その試行錯誤の上に新しい成果を創出する営みです。
強いマーケティング組織を創ることで、企業は、顧客・市場とその変化を捉える認識力、その認識に対応するための思考力・課題抽出力、そして真に価値のあるアクションを導きだし実行する課題解決力を持つことができます。
が
課題解決をサポート!
マーケティングは「伝える技術」ではなく、「ステークホルダーとの関係を更新し続ける力」
マーケティングを“販促”や“広告活動”とほぼ同義と捉えている企業、まだまだ多いです。
もちろん、よりよい販促や広告活動を行うための「伝える技術」は重要な武器ですが、それはあくまでマーケティングに求めるべきものの一部でしかありません。
本当にマーケティングに求めるべきこと、マーケティング活動の本質は、顧客や市場との関係性そのものを更新し続ける営みです。まさにいま、そしてこれから、
- 顧客が本当に困っていること/求めていることは何なのか?
- 自社はどのような文脈で、どんな価値をどんなカタチで届けるべきか?
- その価値は、どう表現され、どう体験されるべきか?
これを顧客や市場と関わりつつ、データや事象も踏まえながら多面的にとらえることを起点に考え、具体的な解に落とし込んでいく。価値を伝えるだけでなく、商品やサービスそのものを見直し、届け方のストーリーを描き直し、顧客とのかかわり方全体を再構築する。
その統合的な設計と実践を通じ、常に顧客や市場を中心とする重要なステークホルダーとの関係を更新しつづけることがマーケティングの本質です。
だからこそ、より強いマーケティング能力を組織的に獲得し「生き抜く力」の向上させることが、新たな市場を創出し自社をとりまく世界を広げていきたい企業の強力な組織基盤となりえるのです。
が
プロをマッチング!
最初の一歩は、販促やコミュニケーションでもかまわない
とはいえ、日々の事業運営の現場でまず現れるのは、もっと切実で生々しい課題です。
- SNSを頑張っているが、思うように反応がない
- プレスリリースを配信しても、なんの問い合わせもおきない
- せっかく展示会に出ても、その場限りで終わってしまう
- よい商品をつくっても、認知されずに埋もれてしまう
- サービスをよりよく磨きあげても、その価値が理解されづらい。
- 一度買ってくれたお客様から、継続購買を引き出せない
- 制作会社に頼んでも、成果もノウハウも社内に残らない
このような悩みが、マーケティングに関連する問題として日々の業務に溢れています。
特に、顧客や市場に向けて「伝える技術」に関する悩みごとは、マーケティングの実践課題としてしばしぶつかるものです。
ただ重要なのは、これらの実践課題を小手先のテクニックで処理してしまわないことです。
伝え方や見え方を見直すことは、単なる部分最適の業務改善ではなく、組織のマーケティング思考と感度を磨くきっかけになり「より必要とされる存在」への第一歩となる。
そう捉えることから、強いマーケティング組織創りの第一歩が始まります。
「誰かを雇う」よりも、今いる人たちの中に「考える力」を育てる
「うちにはマーケティング経験者がいないから…」
そうおっしゃる企業は少なくありません。けれど私は、マーケティング組織の可能性は「今いる人材の中」にこそあると信じています。
なぜなら、レベルの高いマーケティング活動に必要なコアスキルは、決して一部のプロフェッショナルだけが持つ特殊なスキルではないからです。
本当に必要なコアスキルは、「観察する」「仮説を立てる」「言語化する」「カタチにする」「検証する」というスキルと、それらの活動を俯瞰してみる「メタ認知」の力です。
たとえばこんなプロセスです:
- 顧客の声や行動を観察し、「どんな背景や課題があるのか?」と問いを立てる
- その問いに対する答えを、仮説として持ち、その仮説をさまざまな角度から検証してみる。
- 有力そうな仮説に対して自社が提供できる価値や解を、他者とも共有できるよう言語化し整理する。
- 提供できる価値や解を適切なチャネルや表現に具体化しカタチにして、実行してみる
- 実際の反応を見て、仮説と現実の差をふり返り、次の一手に活かす。
このようなプロセスを、属人的ではなく組織の共通言語として展開していくこと。
これが、強いマーケティング組織の第一歩となる「ひとりひとりのマーケティング感度・スキルの向上」と「マーケティング思考の組織OS化」につながっていきます。
例えば以前、私がマーケティング部長を務めた会社では、週に一度のグループでのコーチングという方法でこのプロセスを回していました。マーケティングメンバー4人程度と私で、お互いの先週の振り返りと今週の計画を共有し、コーチングしあうのです。ここでのポイントは「教える/指導する」場ではなく「お互いに学びあう」場としてグループでのコーチングを実践したことです。
なぜこのような方法を取ったかといえば、このプロセスで必要なのは「マーケティングの教科書やあるべき論を学ぶこと」ではなく「お互いの意図や悩みを把握しつつ、より効果的な活動を考え実行するための学びあいを通じ、実践知を深めること」だからです。
こうしたプロセスを経て変わっていく現場を、私は何度も見てきました。
もちろん、この道のりを進むのは簡単ではありません。グループコーチングの中でも、そもそもの問いかけを筋良く着眼できるのか、そのあとの思考と具体化を的外れにならず実践できるのか。新しいチャレンジにはつきまとう生産性の谷が、ここにも存在しがちです。
そこで効率的で有意義な成長速度を実現させるために必要なのが、「問いの立て方」や「考えの構造」を示唆し、メンバーの思考を導くメンター的な存在です。上記のグループコーチングをメンバー任せにせず、必ず私ないしある程度マーケティングをリードできるメンバーを入れていたのはそのためです。
このような方法は組織としてのマーケティングスキルや思考の定着におすすめの方法です。
外注か採用か迷ったら
へ相談!
外部パートナーを「任せる相手」ではなく、「共につくる伴走者」に
ここで誤解してほしくないのは、すべてを内製化しようという話ではないということです。
広告や制作、PR、リサーチなど、外部パートナーと協働すべき領域は多く存在します。
ただし、その関係性は「丸投げ」ではなく、「共創」へと変える必要があるのです。
外部パートナーの力を真に引き出すには、依頼する側にこそ、考える軸と判断力が必要です:
- この施策は、どんな仮説に基づいているのか?
- 何を目的に、誰に向けて、何を伝えどんな変化をもたらしたいのか?
- 実施後に、何をもって成果とするのか?
こうした設計を内側で担い、より高度に外部パートナーの力を引き出せるようになっていくことが、マーケティング組織としての成熟を示します。その結果として、外部パートナーの能力が「瞬間的な借り物」ではなく、いつでも引き出しうる「自社の筋力」となっていきます。
逆に、この力があればこれまでできなかった課題解決もグッと近づいてきます。私が以前ブランドマネジメントを担っていたあるブランドでは、これまで以上に精緻なブランド投資の効果測定・検証のためのスキーム開発を必要としていました。しかしそれは自社の力だけでは不可能で、パッケージ的に外部に存在するものでもありませんでした。
そこで、その実現のために必要なマーケティング上の設計を明確にし、関係各社に相談する中で、大手広告会社2社、デジタル広告会社2社、プラットフォーマー1社に横ぐしを通すスキームを作り上げ、課題解決に至ることができました。これは各パートナーの力を引き出し、成果創出する仲間として共創体制を創れたからこそできたことです。私がこのチームを外れる際に大手広告会社の営業担当の方から「当社チームがこんなややこしいことをモチベ高くやることができたのは得意先があなただったからです、この先このチームのモチベーションをどうすればいいんですか!」と怒られたのは、外部パートナーの力を高度に引き出し、価値の高い共創体制を生んだ結果として、忘れることができません。
「伝える組織」は、やがて「変える組織」へ進化する
伝える力を育てることは、ゴールではありません。
むしろ、それはマーケティング組織としての“入口”にすぎません。
強いマーケティング能力を得るために、伝え方に本気で向き合うことで、組織は次第にもっと根源的な問いに向かっていきます。
- 「私たちは、誰のどんな課題を解決するために存在しているのか?」
- 「そもそも、今の事業や商品は、どんな前提でつくられているのか?」
- 「市場が変化する中で、何を変え、何を守るべきなのか?」
こうした問いに組織で向き合えるようになると、マーケティングはもはや一部門ではなく、事業変革の中核として機能し始めます。
それは、商品開発や価格戦略、サービス設計や営業の在り方すら巻き込みながら、企業全体を「変化に応答できる体質」へと変えていく営みです。
自社にぴったりのマーケターを
スピードアサイン!
最後に──マーケティングとは、未来を見つける力である
言いかえるならマーケティングとは、顧客と市場の変化に耳をすまし、そこから未来の兆しを見出す力です。
そしてそれを、社内で実践し、言葉にし、形にし、広げていくことのできる企業こそが、持続的な成長を手に入れられるのだと、私は信じています。
「うちには専門人材がいないから」
「今はやるだけで手一杯で」
そうした状態からでも、マーケティング組織は必ず育てられます。
むしろ、その一歩を「今いる人たち」で踏み出すことができた企業こそが、
これからの変化の時代を、しなやかに、そして力強く進んでいけるのではないでしょうか。
そのための伴走は私が一番得意とするところです。
強いマーケティング組織・能力を育み「生き抜く力」の高い事業体へと成長する。
そんな未来を、ぜひ一緒に描いていきましょう。
経験豊富なマーケターがすぐ見つかる
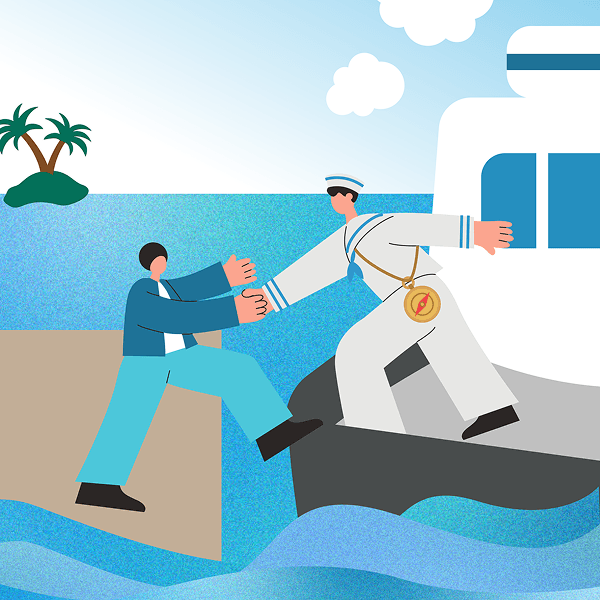
マーケティングDXなら
カイコク!!!
国内最大級※のマーケティング特化型複業マッチングサービス
※株式会社Habiny調べ(2025年7月時点)。マーケティング特化型副業サービスの登録者数を比較。

この記事を書いた人
松崎充克
大手広告代理店×コンサルティング会社×スタートアップ出身
大手広告会社で12年に渡り多様なマーケティングのあり方を学んだ後、大手企業・スタートアップ企業のブランディング・マーケティング責任者を経験。その後大手コンサルティング会社に勤務。20年以上の一貫したマーケティングキャリアを通じブランド戦略構築・新製品開発からダイレクトマーケティング・カスタマーサクセスまで幅広く経験。